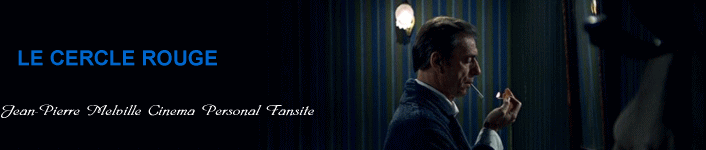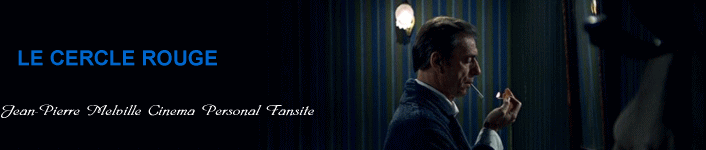BIOGRAPHY
 
ジャン=ピエール・メルヴィル
Jean-Pierre Melville
(1917 - 1973) |
フランスの映画監督。
1917年10月20日、パリ生まれ。
1973年8月2日没。
本名ジャン=ピエール・クロード・グランバック Jean-Pierre Claude Grumbach。
父親は実業家のジュール・グランバック Jules Grumbach(1875年7月30日、ベルフォール生まれ、1932年没)。
母親はベルト・グランバック Berthe Grumbach(1877年生まれ、1966年没)。
両親はいとこ同士だった。
祖父は肉屋のジャック・グランバック Jacques Grumbach(1841年9月3日、ベルフォール生まれ、1895年2月15日、ベルフォールにて没)。
曽祖父は肉屋のアブラム・グランバック Abraham Grumbach(1812年10月31日、ヴィッテンハイム生まれ、1879年9月6日、ベルフォールにて没)。
メルヴィルの先祖は東方ユダヤ人(アシュケナージム)で、1840年代にアルザスのすぐ南に位置するフランシュ・コンテ地方のベルフォールに移住。
推測になるが、おそらく1900年前後にパリ近郊に一家で移住してきたものと思われる。
ユダヤ系の裕福な家庭に育ったメルヴィルは、6歳の頃にはパテ・ベビー社の9.5ミリのカメラと映写機を父に買ってもらい、目に付くすべてのものを撮っていたという。
しかし、撮るより観る方が好きだったらしく、10代になると日々映画館に通いつめるようになる。
「私は一日を朝9時に映画館で始め、午前3時にやはり映画館で終えたものさ。どうにも我慢ができなかった。始終、ずっと、休みなく映画をむさぼりたいというこの絶対的な欲求を抑えられなかったんだ。」
彼はフランス映画よりもむしろアメリカ映画に熱狂し、好きな映画監督としてすぐさま63人の名を挙げるほどだった。
特にフランク・キャプラ、ジョン・フォード、ウィリアム・ワイラーの3人を好んだというが、このリストの中にチャップリンが入っていない理由はチャップリンが“神様”だからだという。(63人のリストはこちらを参照。ちなみに、戦後の監督ではジョン・ヒューストンに特に私淑しており、中でも『アスファルト・ジャングル』は最も偉大な映画の1本と語っている)
1937年10月から40年9月まで兵役に服す。この間に第二次世界大戦が勃発。
この頃から崇拝する作家ハーマン・メルヴィルの名から取って、ジャン=ピエール・メルヴィルと名乗るようになる。
「(メルヴィルに変えたのは)一人の作家、他の誰よりも私を感動させた一人のクリエイターへの、純粋な称賛と、その人物と一体化したいとの欲望からだ。」
40年5月の連合軍ダンケルク撤退開始後、フランス軍の一員としてイギリスに渡る。
除隊後はフランスでレジスタンス活動に加わり、後に密かにロンドンへ行って、志願して英国軍に参加。
その後、ド・ゴール率いる自由フランス軍に入った。
中でも、レジスタンス活動に加わった経験は、後々まで彼の創作活動に決定的な影響を与えた。
なお、この時期でもメルヴィルの映画に対する情熱が衰えることはなかったことは次の証言にも明らかだ。
「1943年にロンドンに着くと、私は8日間の休暇中に27本の映画を観たんだ。」
1945年、復員後、映画監督になる手始めとして助監督見習証をもらおうとするが、共産党の息のかかった映画技術者組合に加入することに抵抗したため果たせず、自らのプロダクションを設立。
1946年、短編処女作『ある道化師の二十四時間』を監督製作。
1947年、自らの撮影所「ステュディオ・ジェンネル」を設立し、長編処女作『海の沈黙』(ヴォルコール原作)を監督製作。
この作品を製作するに当たって、彼は原作者ヴォルコールの許可を得られなかったばかりか、映画技術者組合に入っていなかったために他のプロデューサーたちから度重なる妨害を受けるが、完成した作品は高い評価を受ける。
「『海の沈黙』ができて23年だが(1970年当時)、あの映画は、反映画的な物語の映画化という点において、今日新機軸とみなされている他の試みよりも先に作られたんだ。」
|

『海の沈黙』撮影中の貴重なスナップ |
また、この作品は、自主制作、低予算、ロケ撮影、無名のキャスト、少人数のスタッフなど、後のヌーヴェル・ヴァーグに先んじた撮影方法で製作されたという点でも大変注目される作品である。
メルヴィルが後にヌーヴェル・ヴァーグの“父”とか“先駆者”と称された所以であるが、彼自身のヌーヴェル・ヴァーグに対する見方は極めてクールである。
「まったく、『ヌーヴェル・ヴァーグ・スタイル』なんてものは存在しないよ。ヌーヴェル・ヴァーグは経済的に映画を撮る一つの方法に過ぎない。それだけさ・・・。」
ちなみに、以後メルヴィルの長年の盟友となり、また後にヌーヴェル・ヴァーグのみならず、フランスの代表的キャメラマンとなるアンリ・ドカ(ドカエ)を見出したのがこの作品であることも決して忘れてはならないだろう。
1949年、『海の沈黙』を観て驚嘆したジャン・コクトーに依頼され『恐るべき子供たち』を監督。
後のフィルム・ノワールとは全く異なる瑞々しい作風のこの作品は、トリュフォー、シャブロルなど若き映画人たちを熱狂させる。
1952年、以前から知り合いだったフロランスという女性と結婚。
1953年、ジュリエット・グレコ、フィリップ・ルメール主演の『この手紙を読むときは』を発表。
メルヴィルが脚本を担当しなかった唯一の作品であり、自身最も気に入らない作品だというこの作品は、いかにも当時のフランス映画らしいメロドラマだが、興行的には成功し、その収益で撮影所を増築することができたという。
1955年、自らパリへのラブレターだと語るモンマルトル界隈の暗黒街を舞台とした作品『賭博師ボブ』を発表。
ジョン・ヒューストンの『アスファルト・ジャングル』の影響下にある犯罪映画であり、ユーモアに溢れた小粋な作品であるこの作品は、興行的には当たらなかったものの、やはり、のちのヌーヴェル・ヴァーグの連中の熱烈な支持を得る。
また、この作品以降、73年の急死に至るまでの間、暗黒街を舞台としたフィルム・ノワールを次々と発表。
“メルヴィル・タッチ”とも言われるストイックでクールな映像美で、名声を得ることになる。
1958年、ニューヨークに渡り、『マンハッタンの二人の男』を監督。
アメリカで映画を撮ることは、彼の長年の念願であったが、この作品で、彼は主役の一人であるモロー役を俳優として演じた。
1959年、彼を崇拝していたジャン=リュック・ゴダールに乞われて、その監督作『勝手にしやがれ』に空港でインタビューを受ける作家役として出演。
『マンハッタンの二人の男』のモロー役を始め、俳優としての顔もあるメルヴィルだが、世間的に最も有名な“彼の姿”は間違いなく『勝手にしやがれ』に記録されているそれだろう。
|

『勝手にしやがれ』のメルヴィル出演のワンシーンから |
1961年、ジャン=ポール・ベルモンド、エマニュエル・リヴァを主演に迎えた『モラン神父』を発表。
ベルモンドはもちろん、特にエマニュエル・リヴァの優れた演技を引き出したこの作品は、やはりレジスタンス運動を母体としながらも、彼の数少ない“女性映画”の秀作として高い評価を受けた作品であった。
結果、この作品は、ヴェネチア国際映画祭ヴェネチア市グランプリを受賞したが、メルヴィルが生前受賞した映画賞はこれくらいで、映画賞とは全くと言ってよいほど縁のない映画人生を送ったことになる。(なお、2006年、『影の軍隊』がアメリカで初めて公開され、LA映画批評家協会賞、NY映画批評家協会賞をダブル受賞)
なお、ベルモンドとは以後、『いぬ』、『フェルショー家の長男』と3作続けて映画を撮ることになるが、中でも『いぬ』は日本で初めて公開されたメルヴィル作品であるとともに、フィルム・ノワールの傑作として今なお賞賛の声の絶えぬ傑作である。
また、ジョルジュ・シムノン原作の『フェルショー家の長男』は、アメリカを舞台としたメルヴィル初のカラー作品。
1964年、セルジュ・レジアニ、シモーヌ・シニョレ、リノ・ヴァンチュラらをキャスティングした『ギャング』の企画を立てるが、ある事情によって流れてしまう。
「1964年から1966年までというのは、私にとって、不遇な時期だったよ!」
ちなみに、母親のベルト・グランバックが1966年に亡くなっている。
この後、『ギャング』はメルヴィルの手を離れ、ドニ・ド・ラ・パテリエール監督による撮影の計画が進行していたが、1966年、突如として『ギャング』を監督することになる。
クランクイン4日前に監督をオファーされるという、困難な状況の中、『ギャング』は完成するが、作品は彼の円熟した技量によって優れた出来栄えを示し、興行的にも、この時点でメルヴィルの作品中、最も成功した映画となった。
この作品に対する彼自身の自負のほどは次の言葉にも顕著である。
「『ボブ』は私にとっては犯罪映画ではなくて風俗喜劇だ。だが『ギャング』はフィルム・ノワールなんだ。」
なおメルヴィル作品中、ジョゼ・ジョヴァンニ原作、脚本(メルヴィルと共同)の作品は残念ながらこの1本だけである。
1967年、以前から熱望していたアラン・ドロンを初めて主演に迎え、独自のストイシズムに貫かれた『サムライ』を発表。
美と存在感の際立っていた当時のアラン・ドロンの魅力を最大限に引き出したこの作品の素晴らしさは、今なお観る者を魅了してやまず、メルヴィルのみならず、ドロンのベスト作という呼び声も高い。
ところが、『サムライ』撮影中の同年6月29日、自らの撮影所「ステュディオ・ジェンネル」が火災で消失するという不運に見舞われる。
自らの映画界からの独立の象徴であり、文字通り“牙城”であったスタジオの消失という災難に彼が受けた心の傷の大きさは想像に難くないが、当時彼はそのことを同業者たちには一切話そうとしなかったという。
|

『影の軍隊』撮影時のメルヴィル |
1969年、ジョセフ・ケッセルの原作を基に、自らのレジスタンス活動を反映したライフワークとも言える作品『影の軍隊』を発表。
長らく映画化を熱望してきただけに、メルヴィル自身「自らの最良の作品」と語るこの作品は、発表当時フランス国内では思うような評価を得られなかったが、彼の緊張感ある演出、そして俳優陣の渾身の演技によって悲劇性の秀でた見事な出来栄えを示している。
この作品は、2006年になってアメリカで初めて公開され、二つの批評家協会賞を受けたが、発表当時フランスで必ずしも当たらなかったこの作品が、発表後40年近くたってアメリカの批評家たちに絶賛されるとは彼自身想像すらしていなかったに違いない。
1970年、アラン・ドロン、イヴ・モンタン、ブールヴィルらフランス映画のスターをずらりと揃えた『仁義』を発表。
女性が全くと言ってよいほど出てこないという、彼らしい“男性映画”であり、それとともに、彼の犯罪映画の集大成と言えるこの作品は、公開直前のブールヴィルの死去という話題性もあって、当時フランス国内で大ヒットを記録した。
1972年、アラン・ドロン、カトリーヌ・ドヌーヴの初めての顔合わせとなる話題作『リスボン特急』を発表、結果として惜しくも遺作となる。
|

『リスボン特急』撮影時のメルヴィルとアラン・ドロン |
1973年8月2日、心臓発作にて急逝。享年55歳。
次回作としてイヴ・モンタン主演の作品を計画中だったという。
30年近い創作活動にもかかわらず、完成した作品は13本と寡作であった。
なお、メルヴィルは、パリ近郊のパンタン(Pantin)墓地に眠っている。
なお、この文章に掲載したメルヴィルの言葉(「」で括られた部分)は「サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生」(ルイ・ノゲイラ著 井上真希訳 晶文社刊)から引用したものです。 |
|
French Box Officeによるメルヴィル作品のフランス国内における観客動員数記録
(引用、参考−Ginette Vincendeau著「Jean-Pierre Melville An American In Paris」) |
| 公開日 |
タイトル |
観客数
(フランス国内) |
観客数
(パリ市内) |
| 1949年4月22日 |
『海の沈黙』 Le Silence de la mer |
1,371,687 |
464,032 |
| 1950年3月29日 |
『恐るべき子供たち』 Les Enfants terribles |
719,844 |
255,224 |
| 1953年11月11日 |
『この手紙を読むときは』 Quand tu liras cette lettre |
1,160,986 |
255,746 |
| 1956年8月24日 |
『賭博師ボブ』 Bob le Flambeur |
716,920 |
221,659 |
| 1959年10月16日 |
『マンハッタンの二人の男』 Deux hommes dans Manhattan |
308,524 |
96,490 |
| 1961年9月22日 |
『モラン神父』 Leon Morin, pretre |
1,702,860 |
328,651 |
| 1963年2月8日 |
『いぬ』 Le Doulos |
1,475,391 |
485,186 |
| 1963年10月2日 |
『フェルショー家の長男』 L'Aine des Ferchaux |
1,484,948 |
337,934 |
| 1966年11月2日 |
『ギャング』 Le Deuxieme Souffle |
1,912,749 |
647,857 |
| 1967年10月25日 |
『サムライ』 Le Samourai |
1,932,372 |
508,017 |
| 1969年9月12日 |
『影の軍隊』 L'Armee des ombres |
1,401,822 |
338,535 |
| 1970年9月21日 |
『仁義』 Le Cercle rouge |
4,339,821 |
911,338 |
| 1972年10月25日 |
『リスボン特急』 Un flic |
2,832,912 |
677,411 |
|
|
|