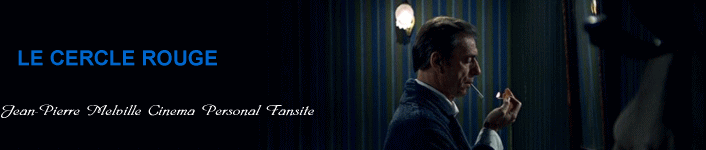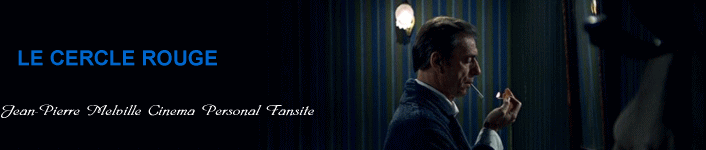| �X�^�b�t |
| ����F |
�������B���E�v�� Melville Productions |
| �����\�F |
�W����=�s�G�[���E�������B�� Jean-Pierre Melville |
| ���F |
�s�G�[���E�u�����x���W�F Pierre Braunberger |
| �r�{�E�ēF |
�W����=�s�G�[���E�������B�� Jean-Pierre Melville |
| �B�e�ēF |
�M���X�^�[���E���[�� Gustave Raulet |
| ���F |
�A���h���E���B���[�� André Villard |
| ���ēF |
�J�����X�E���B�����f�{ Carlos Villardebo |
| ���F |
�~�V�F���E�N���}�� Michel Clément |
| ���y�F |
�A�����E�J�b�Z�� Henri Cassel |
| �ҏW�F |
���j�[�N�E�{�m Monique Bonnot |
|
| �L���X�g |
| �����t�F |
�x�r Béby |
| �����t�F |
�}�C�X Maïss |
| �����t�̍ȁF |
�x�r�v�l Madame Béby |
|
| ���m�N�� |
| 22���i17���Ƃ̋L�^������B�Ǘ��l���L��DVD�ł�18���j�B1946�N�B�e�B |
|
|
�X�^�b�t��L���X�g���̃f�[�^�Ɋւ��܂��ẮA����u�T�����C�v�i���C�E�m�Q�C�����A���^���A�����Њ��j�A�u�L�l�}�{��@1973�@��616�v�i�V�l�E�u���{�[�@�W����=�s�G�[���E�������B���Ǔ��i1�j�R�c�G��j�A�uJean-Pierre
Melville/An American in Paris�v�iGinette
Vincendeau���j��3�����Q�l�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B
�܂��A�X�^�b�t�̖�E�����A�f��{�҂̃G���h�N���W�b�g�Ƃ͑����\�L���قȂ�Ǝv���镔�����������܂��B |
|
| ���r���[ |
�q���̍��T�[�J�X���D���������Ƃ����������B�����A�����t������ɎB�����Z�҉f��B
���я�����ł���w�C�̒��فx�ȑO�ɎB�����A���^�����̏�����ł���A�����Ŋ��ɐ���E�r�{�E�ē����C���Ă��܂��B
��͂�A������܂����������J��i�ŁA�g���̍�i�h�ł��鍡����ς邱�Ƃ͂܂��s�\���Ǝ����v���Ă��܂������A���̍�i�����^�����C�O��DVD���܂�Ɏs��ɏo�邱�Ƃ�����A�������̉��b�ł��̍�i���ς邱�Ƃ��ł��܂����B
���̓��V�A��DVD����ɓ���܂������A�c�O�Ȃ���p�ꎚ�����炠��܂���̂ŁA���t�͑S��������܂���B�i�؍��Ղɂ͉p�ꎚ�������^����Ă���悤�ł��j
�������A�T�C�����g�I�Ȗ��킢�̔Z����i�ł��̂ŁA�f�������ςĂ��Ă����Ɗy���߂܂��B
���e�́A�{���̓����t�ł���A���ۂɃ������B���̗F�l�������Ƃ����x�r���N�p���āA�����t�̈����`���Ă��܂��B
�Ƃ͂����A20�����x�̒Z�҂ł��̂ŁA�S�̗̂���͑�G�c�Ƃ����Α�G�c�B
�������B�����A�g�p�����t�B�����̗Ȃǂ̗��R���炱�̍�i���C�ɓ����Ă��Ȃ������̂̓��C�E�m�Q�C�����u�T�����C�v�ł̃C���^�r���[�ɂ����炩�ł����A���ۂɂ��̍�i�������ς܂��ƁA�{�l�������قǂɂ͉f���ʂł̌��_���ڂɕt���킯�ł��Ȃ��A���e���Ȃ��Ȃ����̂��鏬�i���Ǝv���Ă��܂����̂̓t�@�����ۛ��ڂł��傤���B
���o�ɂ��ςɃZ�R�Z�R�����Ƃ��낪�Ȃ���炩�Ȉ�ۂ̋�����i�ŁA�x�r�[���A�Q�O�ɐ̂̎ʐ^������V�[�N�G���X�ȂǁA�Â��ǂ�����ւ̃m�X�^���W�[�����������܂��B
�܂��A�Z���t�͂Ȃ��A���ׂăi���[�V�����Ői�s���܂��B
���Ȃ݂ɁA�剉�̃x�r�̓��x�[���E�u���b�\���ē̑�1��w�������Ɓx�i34�N�@�Z�ҁ@���{�����J�j�̎���������Ă��邻���ł��B�i�����j |
|
| ���炷���i�̘^�FFaux�l�j |
�u�����Ȑl�������킹��̂͂��炵���d�����B�i�E�a�E�|�N�����v�B�i�i�E�a�E�|�N�����̓����G�[���̖{���j�B
��̃����}���g���A�s�K�[���n��ŁA�V���G�b�g�̖X�q�̒j���r���v������B
11��50�����B
���h���m�E�T�[�J�X�ł͓����t�x�r�ƃ}�C�X�̏o�������I��낤�Ƃ��Ă���B
�h��Ȉߏւ̃}�C�X�͉����ɒ݂邳�ꂽ���̓������r����Œ@���A�؋Ղ̂悤�ɑt�ł�B
�x�r�̓M�^�[�Ŕ��t����B
�o�������I���ƁA�ނ�͊y���Ń��C�N�𗎂Ƃ��f��ɖ߂�B
�x�r�̎���ł͔ނ̍Ȃ��C���̌���U���Ȃ���A�ނ�҂B
�ނ́u�܂��X�p�Q�b�e�C���v�ƕ���������Ȃ���X�p�Q�b�e�B��H�ׂ�B
�x�r�͐Q���ɓ���B
�}�h���b�h���܂�̓����t�u�u�����u���v���ƃW�F���j���E���h���m�i1849�|1912�j�̒����B�i�W�F���j���̑��q�W�F���[���i1907�|98�j��1928�N�Ɂu�����t�T�[�J�X�v���h���m�E�T�[�J�X��ݗ��j�B
�A�J�f�~�[����̍�ƂŃR���f�B�E�t�����Z�[�Y���x�z�l�����߂��W���[���E�N�����e�B�i1840�|1913�j�ɂ��A���h���m�͎��ɂ������q�����A���̑��݂ɂ���ċ~�����i�N�����e�B�́A1886�N�ɁA���h���m�ɂ��Ă̒Z�ҁu�u�����u���v�������Ă���j�B
�~�X�^���Q�b�g�A�A���x�[���E�v���W�����i�w�b���̉����̉��x�j�Ȃǃx�r�̉ߋ��̋����҂̎ʐ^���ǖʂ�����B
�Ō�Ƀh�A�e�̃W���[���E�N�����e�B�̎ʐ^�B
�Q��O�ɔނ̓x�b�h�ŁA�Z���W���i�{�������X�E�t�F�I�f�B�G�[���j�́u�T�[�J�X�̓��v�i45�N�j�Ƃ����{���J���B
���ɂ̓A���g�l�Ɣނւ̒��҂̌������菑���ŏ������܂�Ă���B
�����ăg���X�^���E���~�́u���������v�i46�N�j�Ƃ����{�B������ɂ��x�r�ւ̎菑���̒��҂̌������B
�x�r�͑z���o�̎ʐ^����t�l�܂��������J���B
�y���������A�W�����E���S�[�A�̎�W�����W���X�i�{���W�����W���E�M�u�[���j�A���C�����E�R���f�B�i�w���R���䓙�Ɂx�j�A�w�������x�̃}���Z���E�_���I�i�w�]���x�j�A�w�������x�̃W���E�}���K���e�B�X�i�w�A�^�����g���x�j�A�C�^���A�̕s���o�̃W���O���[�A�G�����R�E���X�e���i1896�|1931�j�A�A���g�l�B
�A���g�l�̎���A�x�r�̑��_�̓}�C�X�ɑւ�����B
�x�r�̕��̓����t�A�E�O�X�g�E�t���f�B�A�j�i1846�|1936�j���Ƒ��Ɉ͂܂ꎀ�ƁA�x�r�̌Z�E�B���[�i1871�|1947�j�̃E�B���[�E�T�[�J�X�A���͂Ȃ��x�������̃P�[�q�j�E�J�t�F�̑O�̃x�r�̎ʐ^�B
�O���E�`���E�}�[�N�X�i�}���N�X�j�̃T�C������ʐ^�B
�l�O�X�A�a�m�A�x���A�ɒB�j�ɕ������Ⴂ���̃x�r�̎ʐ^�B
�t���f�B�A�j��Ƃ́A�l�̓��̏�ɐl�������A����ɂ��̓��̏�ɐl�����댯�ȋȌ|�̎ʐ^�B
�Ȍ|�t�ɂȂ���18�̃x�r�̎ʐ^�B
�{��u�����ނ͈����X�E�B���O�ƈꏏ�ɋF��B
�`���̖X�q�̒j���Èłʼn����̉�������点��V���G�b�g�B
���A�x�r�͖ڊo�܂����v�ŋN����B
�����x�b�h����o�čs���B
�ނ̍Ȃ��M���R�[�q�[�Ǝ莆�������Ă���B
�����t�ɂȂ肽���Ƃ����W�Δ��̏��N����̎莆���B
�O�o�����x�r�͖X�q��Y�ꂽ���ƂɋC�Â��A���J�ŃA�p�[�g�̏�̊K�̍Ȃ��ĂԂƁA�Ȃ��X�q�𓊂���B
�x�r�̓A�p�[�g�̐^�������̃����^�����O����i���j�ɍs���B
������o���x�r�́A�O����������Ă����Ⴂ�����Ɍ��Ƃ�A�Ȃɓ{����B
�ނ͎d���ĉ��ɑ���Ȃ��悤�C�����Ȃ���A�ߏ��̍s�����̃J�t�F�ɍs���A�X�̒�����A�q�ɖX�q�ƃR�C�����g�����|��������B
�}�C�X�Ɨ����������x�r�́A���s�b�N�X�̃J�t�F�̃e���X�ŁA�ʕ�����̕w�l�A�V����ǂ݂Ȃ�������ē]�Ԑa�m�A���̑��̒ʍs�l�������ώ@����B
�d���̎��Ԃ�����ƁA�}�C�X�ƁA�����X�E�B���O��A�ꂽ�x�r�͎ԂŃ��h���m�ɍs���A���C�N����B
�}�C�X�ِ͈F�̌o�����������t���B
1905�N�ɁA�g�D�[�����̃I�y�������Ύ��ɂȂ������A�������������l�_���T�[����t�Ƃ��Ď��Â��A�ޏ��������������̂����������ł��̓��ɓ������B
�}�C�X�̖����}�C�X�̒��t������`���B
�}�C�X�ƃx�r�͕���ɏオ��B
���̔ӂ̖��˕��̌|�i�����ŏ��߂ă}�C�X�ƃx�r�̓����^���̐���������j�ɂ͌ߌ�̃��s�b�N�X�ł̊ώ@����������Ă���B
�����t���Ђ��ς������̂͂����B
�x�r���}�C�X�ɂЂ��ς������B
�V���G�b�g�̖X�q�̒j���r���v�����Ă���B11��50�����B
|
|