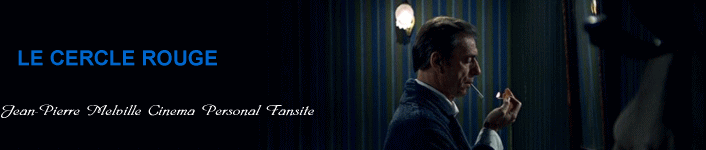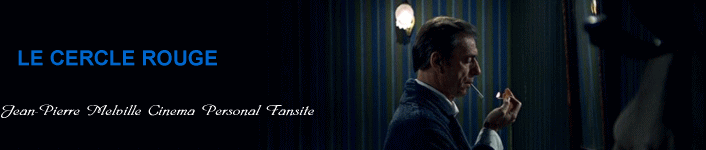| 書籍関連 |
|
サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生 |
ルイ・ノゲイラ著 井上真希訳 晶文社 |
原本は、1970年にルイ・ノゲイラによって行われたメルヴィルへのインタビューを元にフランスで73年に発行された「Le Cinema Selon
Melville,Editions Seghers」。
我が国では、メルヴィル没後30年の2003年に突如翻訳本が発売されました。
ジャン=ピエール・メルヴィルという監督がいかなる人間であるか、また、どれだけ映画を愛していたかを知るにあたって、これ以上の本は存在しません。
翻訳本が発売されたことを含め、まさに奇跡のような本であり、メルヴィルとその作品を知るなら、何はともあれこの一冊!という、まさにメルヴィル・ファン必読・必携の本。
実際、2003年の発売以来、この本が我が国のメルヴィル作品の受容にどれほど多くの貢献を果たしてきたか計り知れません。
データの充実ぶり、メルヴィルの口調を巧みに表現した翻訳、装丁の素晴らしさなど、作りが実にしっかりしている点も嬉しい限り。
メルヴィルの、自作品はもちろん、映画にかける情熱に圧倒されます。 |
|
|
映画伝説 ジャン=ピエール・メルヴィル |
古山敏幸著 フィルムアート社 |
2009年冬、突如として上梓された国内初のメルヴィル作品評伝。
ほぼ同時期にメルヴィル映画の大回顧展が初めて日本で行われたことも嬉しい驚きでしたが、この種の本が世に出たことも同様に大きな驚きでした。
それだけに、待ちに待った感があり、実際、文章も読みやすく、内容も大変面白いので、一気に読み終えてしまいます。
内容は、リアルタイムでメルヴィル作品を観てきたという筋金入りのメルヴィル・ファンの著者が、長編全作品1作1作を丁寧に解説しています。
これまで日本ではほとんど触れられてこなかった事実も含め(例えばメルヴィルがユダヤ人であることをきちんと指摘した書物はこれが初めてでは?)、およそメルヴィル作品に関わる事柄は万遍なく押さえられていると言ってよいのではないでしょうか。
もちろん、この本を通じて知った新事実もたくさんあります。
また、作品を通じてメルヴィルが生きた時代背景、映画界の状況を検証することで、作品論としてだけではなく、一種の社会論、映画作家論となっているのも興味深い点です。
メルヴィル映画を見つめる視線も極めて冷静かつ客観的で、決してファンの贔屓の引き倒しになっていない点も評価できます。
これはメルヴィル作品に関心のある方なら読んで絶対に損のない素晴らしい本であり、ルイ・ノゲイラの『サムライ』と並んでファン必携の本だと断言できます。 |
|
Jean-Pierre Melville: An American in Paris |
Ginette Vincendeau著
Paperback |
2003年に発売されたばかりの洋書(英語)。
Amazon等で簡単に入手できます。
著者は、メルヴィルの海外盤DVDのコメンタリーや解説などにもよく顔を出しているフランス人女性評論家。
メルヴィル研究家と言える人物は世界的にも多くはないと思われますが、この方は、中でも現在最も精力的に啓蒙活動(?)に勤しんでいる人物と言えましょう。
私も所有しておりますが、270ページにも及ぶ大書であり、私の語学力では残念ながら読破するのは至難の技・・・(涙)。
しかし、データも含め、内容は極めて充実している(?)本なので、どこかから翻訳が出ることを期待しましょう・・・。 |

|
フランスの映画作家たち |
田山力哉著 白水社 |
82年刊。戦前から70年代半ばぐらいまでのフランスの映画作家(監督)総勢31人の紹介。
30年代にフランス映画に魅せられて以来の氏のフランス映画への想いが結実したかのような1冊で、特に戦前の作品に対する思い入れが深い様子。
それぞれの時代の概説、トリュフォーとの対話、フランスの映画評論家マルセル・マルタンとの「フランス映画に未来はあるか」と題する対論など、内容も充実。全体的に、なかなか辛辣な評価も目に付きますが、メルヴィルのことはかなり好意的に紹介しています。
この中から「サムライ」に関する文章を紹介します。
「フランス映画独自のペシミズムを基調としながら、感傷などは一切排し、冷たい、クールな演出タッチを貫いた画面は、何か底光りのするような魅惑をたたえていた。メルヴィルの暗黒映画の一つの頂点と言ってよいだろう。いわば、アメリカ映画が、フランス人の感性、知性に叩き抜かれて結晶した美とでも言っておこうか。」 |
|
わがフランス映画誌 |
山田宏一著 平凡社 |
1990年刊のハードカバーで、現在は古本扱いですが、Amazonなどで安く入手できます。
現在は、ワイズ出版から「山田宏一のフランス映画誌」という同じようなタイトルの本が発売されており、内容も若干重なるものがあるので少々混乱しますが、「山田宏一のフランス映画誌」には掲載されていない、この本ならではの注目すべき記事がたくさん掲載されており、フランス映画に興味のある方なら絶対に買って損のない本だと思います。
内容では、「シネマトグラフ年代記」と題した、映画の誕生からトーキーに至るまでのフランス映画の歴史をまとめた記事、そして、なんといっても、ピエール・ブロンベルジェ(プロデューサー)、アレクサンドル・トローネル(美術監督)、フランソワ・トリュフォー(映画監督)、ルイ・マル(映画監督)、アレクサンドル・マルキュス(メーキャップ師)、ジル・ジャコブ(カンヌ映画祭総代表)といった多くの映画人たちのインタビュー記事が読めるのが嬉しいところ。
とりわけ、ジャン・ルノワールやヌーヴェル・ヴァーグ関連の貴重な証言が読めるピエール・ブロンベルジェのインタビューと、撮影監督アンリ・ドカについて多くの証言が読めるルイ・マルのインタビューが興味深いと思います。
また、メルヴィル関係では「山田宏一のフランス映画誌」に掲載されているものと同内容の「ヌーヴェル・ヴァーグ前夜」と題した4ページの記事も掲載されています。 |
|
山田宏一のフランス映画誌 |
山田宏一著 ワイズ出版 |
氏の、フランス映画に関する文章をまとめた一冊。
分厚く3400円と高価ですが、内容の充実ぶりと、その面白さは全くもって無類。メルヴィルの項も二つ収録されていますが、一つはパンフレット「ジャン=ピエール・メルヴィルの世界」に収録されているものと同じものです。
興味深いのは、70年代半ばのアンリ・ドカ(ドカエ)へのインタビューを元に、アラン・ドロンと組んだ「サムライ」以後メルヴィルが通俗化したとの説を述べている点。
「サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生」を合わせて読むと、「仁義」の撮影においてメルヴィルとドカの間に一悶着あったのでは?と思えてなりませんので、ファンとしてはどうかと思ってしまいますが・・・。 |

|
カルチエ・ラタンの夢 フランス映画七十年代 |
中川洋吉著 ワイズ出版 |
70年代のフランス映画は、いまだほとんどの作品が国内DVD化されていない状況であり、一部の作品を除いては日本の映画市場ではほぼ無視されていると言ってもよいかもしれません。
この本は、その当時パリに在住していた著者が、当時のフランスの社会情勢や、時代背景などを踏まえつつ、当時の重要作品や映画監督、俳優等を紹介、解説しています。
内容の目録は…
1「タブーの粉砕」―イブ・ボワッセの場合
2「コンテスタテールが存在しえた時代の生き証人」―ジョルジュ・コンションの世界
3「もう一つのヌーヴェル・ヴァーグ」―ミッシェル・ドラックの場合
4「ポルノ解禁と見せかけのリベラル路線」
5「女性の権利獲得」運動―フランス女性を体現したアニー・ジラルドとロミー・シュナイダー
6「在フランス外国人監督が描く移民問題」
7「右も左も蹴飛ばす異能人間」―ジャン・ヤンの場合
この本で紹介されている作品は、当然、私も未見のものばかりですが、それでもこの本の内容は実に面白く、作品を観たいという思いを強く持ちました。
この時代のフランス映画に関心のある方には是非一読をお勧めしたい素晴らしい本です。
ちなみに、この本で紹介されているイヴ・ボワッセは、メルヴィルの『フェルショー家の長男』で助監督を務めていますし(本の中で『いぬ』の助監督と表記されているのは間違い)、ミッシェル・ドラック(ドラシュ)はメルヴィルの従弟で、メルヴィルの『海の沈黙』、『恐るべき子供たち』では助監督を務めています。 |
|
映画作家論 |
中条省平著 平凡社 |
94年刊。リヴェット、ロメール、トリュフォー、ドゥミ、ゴダールらフランス映画の監督を中心とした、大変読み見応えのある映画評論集。中に「ジャック・ベッケルとジャン=ピエール・メルヴィル」という項目があり、二人の作品を肴にフィルム・ノワール論を展開しています。
氏は「フランスのフィルム・ノワールは、創始者のベッケル、継承・完成者のメルヴィルに尽きる。」と論じ、そのジャンルにおいてはベッケルの『穴』とメルヴィルの『いぬ』が他と隔絶した傑作であると述べています。長くなりますが、中から印象的な文章を紹介しましょう。
「『いぬ』の冒頭の長い長いワン・ショット=ワン・シークェンスを見るだけで、メルヴィルが独創的なスタイルを完成させていることがよく判る。鉄橋とトンネルの下に延々と続く一本道をセルジュ・レジアニが歩いてゆく。彼は鉄橋とトンネルの作る複雑な影の下を通過してゆくのだが、カメラは巧みな動きを加味しつつ、絶えまないトラック・バックで、この光と影の交替に包まれる男の姿を映し出す。映画作家の冷淡なまなざしは、暗黒街の底辺に暮すギャングのいつ果てるとも知れぬ徒労にみちた歩行をつき離して描いているのだが、同時にそこには、なにかクールな優雅さが確かに漂い、高貴さともいえる輝きが感じられるのだ。この冷やかな輝き、冷艶こそがメルヴィル・タッチの真髄である。」 |
|
フランス映画史の誘惑 |
中条 省平著 集英社新書 |
2003年刊。
著者は学習院大学の仏文科教授。
新書でフランス映画の歴史を網羅した内容の本は珍しい(全くない?)ので極めて貴重な本です。
新書ということもあって、手軽に読めるのが良く、特に、映画発祥の流れ~サイレント映画に至るまでの歴史が簡潔にまとめられていて勉強になります。
ただ、フランス映画史とはいっても、監督を中心とした内容で、俳優や女優、製作者や撮影監督、映画音楽などにはほとんど触れられていないのが個人的には残念。
その意味では新書の限界が感じられ、内容的には今一つの感が拭えません。
また、著書『映画作家論』でも分かるように、メルヴィルを高く評価している著者だけに、メルヴィルの項目があるのは嬉しいのですが、ここでは一通りの紹介になっています。
個人的に、この著者の本では『映画作家論』の方がずっと面白いですね。 |
|
フィルムノワールの時代 |
新井達夫著 鳥影社 |
2002年刊の本で、著者は1941年生まれの、CMなどの映像作家。
40~50年代は、ハリウッドにおいてフィルムノワール作品が量産された時代ですが、その時代を、主に映画作家や俳優を通して検証している本です。
あくまで40~50年代のハリウッド産のフィルム・ノワールに対象を絞った本ですので、そのため、メルヴィルなどのフランスのフィルム・ノワールに関する記述はほとんどありませんが、内容はエッセイ風で読みやすく、また、読んでいてワクワクするような面白さや説得力があり、なんとも映画的好奇心を誘発してくれる本です。
また、この本を読み進めることによって、なぜ40年代になってからハリウッドでフィルムノワール作品が量産されるようになったのか、また、その作風はどこから来たのか、などの様々な疑問点が明らかになってゆきます。
スタンバーグやルビッチなどのサイレントの時代まで遡って検証しているので、フィルムノワールがヨーロッパの文化(主にドイツ)からいかに影響を受けているかなども理解しやすいです。
2002年刊の本なので、DVDやビデオ等、作品の視聴情報が現在とはまた異なる部分がありますが、逆に言えば、現在少しずつではあるものの、このジャンルの作品が視聴可能になりつつあることが分かります。
値は少々張るものの、フィルムノワールに関心のある方には一読の価値のある本だと思います。 |
|
幻影シネマ館 |
佐々木譲著 マガジンハウス |
ジャン=ピエール・メルヴィル監督の遺作が『リスボン特急』(72)であることは今さら言うまでもないことですが、この本の著者によれば、実はメルヴィルにはピエール・グラニエ=ドフェール(『離愁』)
と共同監督した『夜のバラ』(73)という遺作があった。
原作はジョゼ・ジョヴァンニ、撮影はアンリ・ドカ、出演者はジャン=ポール・ベルモンド、リノ・ヴァンチュラ、イヴ・モンタン、フランソワ・ペリエ、セルジュ・レジアニ、シモーヌ・シニョレ、カティ・ロジェ…著者はこの映画を88年にパリのシネマテークで観たという…。
メルヴィル・ファンならずとも胸躍るお話です。
しかし、当時メルヴィルと仲違いしていたジョゼ・ジョヴァンニ、アンリ・ドカ、リノ・ヴァンチュラが揃っている点がちょっと怪しい…実は、これは著者の幻、つまりは作り話なのです。
なーんだ、とガッカリすることなかれ。
このメルヴィルの作品に限らず、映画ファンなら誰しも観たくなる、夢のような映画36作品がこの本では紹介されています。
もちろん、すべて著者の“幻影”が語られているわけですが、そのストーリー、エピソードまでがいかにもリアリティある物語ばかり。
宇野亜喜良氏の絵も雰囲気があって魅力的です。 |
|
映画がなければ生きていけない 1999-2002 |
十河進 水曜社 |
2006年の発刊時からずっと気になっていた本ですが、ようやく購入。
著者がメール・マガジン『日刊デジタルクリエイターズ』にて映画コラムを連載していたものを2冊の本に集大成したもので(続編もあり)、600ページ近い分厚い本ですが、平易な文章で綴った文章は奇をてらったところが全く無く、実に読みやすい。
内容は厖大な数の映画を題材に、著者の個人的な出来事や若い頃の思い出等も綴られていますが、それらも読んでいて本当に面白いです。
観ている映画もバラエティ豊かで、特にフランス映画も数多く登場するので、その点も嬉しい。
ちなみに、著者のオールタイム・ベストワンはロベール・アンリコ監督の『冒険者たち』とのことで、その点でも私と趣味が合います(笑)。
また、嬉しいことに著者はメルヴィル・ファンでもあり、メルヴィル作品についての記述もいくつも目に付きます。
その中から印象的な言葉を引用します。
“メルヴィルの映画を一言で表すなら「ストイック」だろうか。禁欲的で厳しい映像が、ゾクゾクするほど素晴らしい。セリフをそぎ落とし、最低限必要なものしか残さない。もちろん、音楽で盛り上げることなど、まったくしない。すべてを映像で語る。(中略)饒舌で意味のない映像が垂れ流されている現在、メルヴィルの映画を見ると、緊張感でいつの間にか背筋がのびてくる。僕も意味のない言葉を喋り散らかしたりしないようにしよう、と厳しく律したくなる。(中略)メルヴィルの映画の放映やビデオを見つけたら、ぜひ、見て欲しい。メルヴィルの映画を見逃しているということは、人生の深さを学ぶチャンスを逃しているということである。人生は、本当は四つの要素で出来ているのである。夢と友情と裏切りと……(それらを描いたメルヴィルの)映画と、である。”(50~52ページ) |
|
映画気分でパリを散歩 |
沢登めぐみ著 ピエ・ブックス |
パリの街の映画舞台880ヵ所を地図と写真で紹介したガイドブック。
紹介されている映画、写真も豊富なのでフランス映画好きには堪らない一冊であり、パリ旅行の際は必携の本と言えるでしょう。
取り上げられている作品は、ヌーヴェル・ヴァーグ作品が比較的多めですが、メルヴィル作品では「恐るべき子供たち」「サムライ」「仁義」のロケ地が紹介されており、中でも「サムライ」でのドロンの足跡が丁寧に紹介されているのがファンには嬉しい限り。
2005年に出版されたばかりの本なので情報も新しいのですが、Amazonでプレミアが付いているということはもう絶版になってしまったのでしょうか。(新品は税込1890円)
運良く私は状態の良い新品を見つけることができましたが、もし絶版だとしたら大変な労作であるだけに残念です。 |
|
ヌーヴェル・ヴァーグの時代―1958‐1963
E/Mブックス |
エスクァイアマガジンジャパン |
その名の通り、ヌーヴェル・ヴァーグとは何かを作品紹介を中心に検証した一冊。
写真が豊富でとても読みやすい本で、メルヴィルでは「マンハッタンの二人の男」「レオン・モラン神父」「いぬ」が取り上げられています。
カラーページでは「いぬ」のフランス語版ポスター、ヌーヴェル・ヴァーグ関連人物名鑑ではメルヴィル、カメラマンのアンリ・ドカエらの紹介も。
ヌーヴェル・ヴァーグに関心のある方なら持っていて損のない一冊です。 |
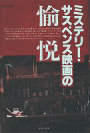
|
ミステリー・サスペンス映画の愉悦 |
シネマハウス |
93年刊。
本の内容は、第1部「ミステリー・サスペンス映画の誘惑 作品138本」と、第2部「ミステリー・サスペンス映画の監督術 監督18人」の二つに大きく分かれ、それぞれが27人の執筆陣によって解説されています。
第1部ではフレンチ・ノワール作品も多く選ばれている中、なぜかメルヴィル作品は1本も選ばれていませんが、第2部の監督18人にメルヴィルが選ばれています。
そこに掲載されている黒田邦雄氏によるメルヴィル論は、『リスボン特急』のラストシーンの解釈に若干疑問があるものの、メルヴィル作品の特徴を捉えていて秀逸。
一部抜粋します。
「正装のギャング映画、ジャン=ピエール・メルヴィルの作品を一口で言うとこうなろうか。彼の映画に登場するギャングたちは、生き方においてもファッションにおいても、犯罪の方法においても、実にスタイリッシュで、決して乱れることがない。」
「メルヴィル映画の男たちは、決してグチをこぼさず、というよりいつも寡黙で、じっと耐えているというふうな男ばかりだ。彼らが中折れ帽にトレンチコートというスタイルを好むのは興味深いが、これはメルヴィルのアメリカ暗黒映画へのオマージュであるとともに、男の軍服という面もかなり考慮する必要がある。彼らは決して流行に合わせたり、個性的なファッションに身を包んだりはしない。軍人に軍服が不可欠なように、ギャングにはギャングの服装、つまり帽子にトレンチコートというのは、ほとんど掟として存在するのだ。」 |
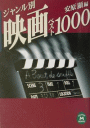
|
ジャンル別 映画ベスト1000 |
安原顕編 学研M文庫 |
平成13年発行。
20人の執筆陣によって、様々なジャンル別に50作ずつの作品がセレクト、紹介されています。
それぞれ作品のの紹介文の長さもまちまちで、また、選者によって作品が重複して選ばれるなど、コンセプトは結構いい加減ですが、かえってそれが選者の本音を引き出しているようで興味深い。
Amazonではそのあたりの評価が賛否両論のようですが、選者の個性が色濃く表れたセレクトと、文章の内容が面白いので、読んでいて飽きません。
索引を入れると600ページを超える分厚い文庫本で、書店では絶版のようですが、現在ならAmazonで古本が安く入手できるようです。(本体の価格は960円)
そして、注目すべきはメルヴィルの作品がいくつか選ばれていることで、上野昂志氏選出の「ハードボイルド ベスト50」に『いぬ』『ギャング』『サムライ』『影の軍隊』が、中条省平氏選出の「フィルム・ノワール ベスト50」に『いぬ』が選ばれています。
この中から、お二人の文章を引用してみます。
上野昂志氏 「六〇年代後半、アメリカのハードボイルド映画が後退する一方で、ジャン=ピエール・メルヴィルのフランス暗黒映画が、モノクロームの陰影もあざやかに浮上する。その意味で、六〇年代後半は、メルヴィルの時代だったのだ。(一部省略) (引用注『ギャング』について)それにしても、プラチナの運搬車を襲う前の、崖の上の道に男たちが集う場面の凄さ。待機する間の緊張と弛緩が入り交じった一時を、荒涼たる風景のなかにあれほど的確に描き出した例は他に見たことがない。」(134~135ページ)
中条省平氏 「フランス製フィルム・ノワールを一人で代表する作家はメルヴィルだ。彼の『ギャング』と『いぬ』だけが、ベッケルの『現金に手を出すな』と『穴』に比肩する。フレンチ・ノワールはベッケルの二本と、メルヴィルの残した七本に尽きるといってもよい。なかでも『いぬ』はクールな輝きにおいて他を断然抜きんでている。」(169~170ページ) |
|
おまえの不幸には、訳がある!
―たけしの上級賢者学講座 |
ビートたけし著 新潮文庫 |
現在は新潮文庫から発売されていますので、簡単に入手できます。
言わずと知れたビートたけしのエッセイ集であり、内容は、主に現代の日本社会に対して、たけし一流の皮肉の効いた、なかなか面白い本です。
中に、「20世紀の100人」として、世界篇50人、日本篇50人ずつの偉人を選んでいるのですが、そのセレクトがまたたけしらしいユニークなもの。
そして、この世界篇50人の中には、海外の映画関係者が監督俳優合わせて11人選ばれており、その中の一人になんとジャン=ピエール・メルヴィルが選ばれているのです。
メルヴィルについてのたけしのコメントは立ち読みでもすぐ読めるものですので、ここでは言及しませんが、一部で指摘されている、たけしの“メルヴィル好き”を立証する貴重な本と言えるでしょう。 |
| 原作関連 |
|
海の沈黙・星への歩み |
ヴェルコール作 河野與一、加藤周一訳
岩波文庫 |
ヴェルコールによって書かれた『海の沈黙』の原作は、フランスがドイツの占領下にあった1942年に発行され、フランス抵抗文学の傑作といわれています。
この岩波文庫版には、『海の沈黙』と『星への歩み』という中篇(ほとんど短編に近い)小説二編が収録されています。
『海の沈黙』だけだと60ページ程と短く、行間も詰まっていないので、一時間もあれば読み終えることができるでしょう。
文章は決して難解ではなく、映画を観たことのない方でも十分内容を理解できるはずです。
私は、この原作本を学生時代にも一度読みましたが、今となってはほとんど記憶にありません。
当時は映画化されていることすら知りませんでしたので、きちんと関心を持って読んだのは今回が初めてといってよいかと思います。
そして、改めて読み直してみて、メルヴィルの映画が、この原作の内容に極めて忠実な映画であることがよく理解できましたし、同時に、この小説が実に感慨深い小説であり、大変な傑作であるということも理解できました。
それだけに映像化は決して簡単ではないと思われますし、ヴェルコールが映画化に反対したことも分からなくはありません。(まして、メルヴィルは当時全くの新人映画監督でもあったわけですから…)
しかしながら、映画『海の沈黙』もまた原作に劣らぬ見事な傑作であることを、この原作本を読んで改めて感じ入った次第です。
『海の沈黙』というタイトルの意味も、本を読んで一層理解が深まりました。 |
|
|
恐るべき子供たち |
コクトー著 中条省平、中条志穂訳
光文社古典新訳文庫 |
ジャン・コクトー原作による『恐るべき子供たち』の初版本は1929年の6月にフランスで出版されていますが、これは2007年に日本で発行された新訳本。
『恐るべき子供たち』の日本語訳本といえば、長らく岩波文庫の鈴木力衛訳のものが一般的であり、私も数年前にチャレンジしましたが、文字が小さくて読みにくい上、訳文も分かりにくいという印象がありました。
岩波文庫の赤版(外国文学)は、読みにくかろうがなんだろうが、それを我慢してでも有難がって読まなくてはいけないという、ある種の権威主義が私の学生時代ぐらいまでは色濃く残っていましたが、昨今の新訳ブームはそういったものに対する反発も多少はあるように思われます。
もちろん、難しいものを読破した時の達成感というか、自己満足はそれはそれで悪いものではありませんが、もっと楽に西洋文学を楽しめるに越したことはないでしょう。
その意味で、今回取り上げる光文社古典新訳文庫は、訳文が平易で大変読みやすい。
文字が大きめな点も、視力がどんどん低下してきている私のような人間にはありがたく、すんなり読みこなすことができました。
また、この本にはコクトー自身によって1934年に書かれた『恐るべき子供たち』のイラストが62点収録されており、これがなんとも味があって魅力的ですし、物語の内容を理解する上でも大変助かります。
また、メルヴィルの映画との関連でいえば、映画が原作に極めて忠実であることが改めてよく理解できましたし、映像化にあたって、コクトーのイラストが大きな助けになったであろうことも想像できました。
同時に、ポール役のエドゥアール・デルミットをメルヴィルがミスキャストと言った意味も理解できたように思います。
逆に、エリザベート役のニコル・ステファーヌは役柄のイメージにピッタリだというように私は感じました。
コクトーのイラストを見ても、エリザベートはニコル・ステファーヌはよく似ているように思ったのは私だけでしょうか。
巻末に訳者・中条省平氏による見事な解説とコクトー年譜付き。 |

|
フェルショー家の兄 |
ジョルジュ・シムノン著 伊藤晃訳
筑摩書房 世界ロマン文庫 |
『フェルショー家の長男』の原作の翻訳本。
この原作は分量も多く、これをそのまま映画化しようと思えば、3時間くらいの長い映画になってしまうのではないでしょうか。(実際の映画は100分ほど)
メルヴィルは、ルイ・ノゲイラ著「サムライ」において、「『フェルショー家の長男』は、シムノンに対してまったく誠実な映画だよ、まったく小説とは無関係だがね。」 と一見矛盾とも取れるような発言をしていますが、実際、この原作を読みますと、メルヴィルの映画とはほとんど別の作品と言ってよいほど物語の設定が異なることがよく分かります。
一つ例を挙げれば、映画はベルモンド演じるミシェル・モーデのボクシングの試合シーンから始まりますが、これは映画版の創作であり、小説にはそのような場面はありません。
他に、簡単に映画と原作の大きな相違点を挙げてみます。
●原作では、フェルショーとモーデが海外に脱出するに至るまでの状況が、モーデの妻の存在も踏まえて非常に丁寧に描かれているが、映画ではこのあたりがバッサリとカットされている。
●原作では、二人がフランスからコロンに逃亡した以後、モーデが出入りする店の主人ジェフと、オランダ人ススカとの関わり、ラストに向かってのモーデの心理の変化が非常にねちっこく描写されているが、映画ではこのあたりは非常にアッサリと描写されている。これに関しては、ラストの設定そのものが原作と映画では全く異なるので当然といえば当然でしょう。(原作ではモーデがフェルショーを殺害します)
また、フェルショーとモーデが渡る国も、映画はアメリカですが、小説はパナマのコロンです。
このように、原作と映画は大きな相違のある作品となっていますが、映画はいまだ国内未公開であり、鑑賞には字幕なしのフランス盤DVDに頼らざるを得ない状況では、その違いを論ってもあまり意味のないことかもしれません。
ところで、それは別として、この原作の小説は実に読んでいて面白かったですね。
あまり大きな声では言えませんが、もしかしたら映画よりも面白いかもしれません。
ただ、小説の方の雰囲気は全体的にかなり陰鬱で(ラスト近くなど、昔読んだドストエフスキーの『罪と罰』を思い出しました)、映画の方がむしろベルモンドのキャラクターゆえか、快活な印象が強くなっています。
ちなみに、タイトルの『フェルショー家の兄』の“兄”が誰を指すかですが、(映画ではシャルル・ヴァネル演じる)デュードネ・フェルショーには共に財を成したエミールという弟がいます。(映画にも僅かですが登場します)
つまり、“フェルショー家の兄”とはデュードネ・フェルショーその人のことであって、ミシェル・モーデのことを指すのではありません。
映画のタイトルのように“兄”ではなく“長男”という表記では誤解の恐れがあると思われます。 |
|
|
おとしまえをつけろ |
ジョゼ・ジョバンニ作 岡村孝一訳
早川書房 |
1968年10月に国内で出版された『ギャング』の原作の邦訳本。(本国での出版は58年4月)
原題の『Le Deuxieme Souffle』の意味は「第二の息吹き」というらしく、この本のタイトルはこの邦訳本オリジナルのものです。
古本屋で見つけましたが、神保町などのミステリー関係の古本屋なら比較的見つけやすいと思います。(ただし、お店によって価格に差があるので注意)
300ページほどで二段構成というかなりの分量ですが、内容は面白いのでどんどん読めます。
映画版とは異なる原作の大きな特徴としては、主に次のような点が挙げられるでしょう。
●ギュは“おやじ”と周囲から言われるくらい、年取った中年という設定。
●マヌーシュは超美人のグラマーという設定。
●ポール・リッチの名前は原作ではヴァンチュール・リッチという名前になっている。
●映画ではポールが兄、ジョーが弟だが、原作では反対にジョーの方が兄という設定。
●マヌーシュには以前ポールという夫がいたが、事故で亡くなっている。
●脱獄後のギュとマヌーシュは肉体的に結ばれる。(映画ではその辺が曖昧)
●ブロ警部の部下のプーボンは大の女好きで、女の尻ばかり追い回している。
●ギュは逃亡後のマルセイユでの生活で、テオの他にジュスタンというポール(マヌーシュの元夫)のいとこの世話になる。
●ギュは警察病院から脱走する際、二人の男の協力を得る。
●ヴァンチュール(ポール)・リッチにはアリスというイカれた妻がいる。
●オルロフはマヌーシュに惚れ、マヌーシュもオルロフに只ならぬ好意を持つ。
●ラストは二人のその後を暗示する幕切れ。
メルヴィルは、ルイ・ノゲイラ著『サムライ』のインタビューにおいて、「オリジナルの映画を撮ったことを自負している」と言っていますが、実際読んでみますと、確かに上記のような差異はあるのですが、全体の大まかなストーリーには差異がないという印象です。 |
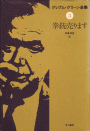
|
拳銃売ります |
グレアム・グリーン作 加島祥造訳
早川書房 |
「かつて私はグレアム・グリーンの大変な名作を一冊読んだが、それをフランク・タトルがアラン・ラッドとヴェロニカ・レイクの出演で映画化した。だが、分裂病患者の描写には大きな欠落があったね。」(引用―「サムライ」ルイ・ノゲイラ著 井上真希訳 晶文社刊 250Pより)
ここでメルヴィル監督によって言及されている、グレアム・グリーンの1936年の小説「拳銃売ります」(「A Gun for Sale」)、フランク・タトル監督の1942年のアメリカ映画『拳銃貸します』(『This
Gun for Hire』)は、ともに『サムライ』の“元ネタ”としても知られています。
実際、この二つの作品に触れますと、フランク・タトルの映画、そして、このグレアム・グリーンの原作が『サムライ』という映画の着想、さらに、その主人公であるジェフ・コステロという孤独な殺し屋のキャラクター造形に大きな影響を与えたことは間違いないと思われます。
もちろん、この原作とフランク・タトルの映画にもさまざまな相違点があります。
このグレアム・グリーンの小説を読んで分かるのは、映画版以上に、主人公の殺し屋レイヴンの凄まじいほどの孤独感がこれでもかと描かれていることです。
原作において、あらゆる他者を信じることができない孤独な人間として描かれているレイヴンは、アンという女との係わりの中で、この女だけは信じられると考えるようになりますが、その女にさえ、最後は裏切られてしまうのです。(映画版ではその辺が非常に曖昧)
また、映画版では、レイヴンの身体的特徴は、左手首にやけどの跡が残っているという設定ですが、原作では、唇の外面に欠陥のある(あえて直接的表現は避けます)という設定となっており、その欠陥が、レイヴンという一人の人間にとって、どれだけ深い心の傷であるか、原作ではしつこいくらいに描かれています。
一方で、ルイ・ノゲイラ著「サムライ」を読みますと、メルヴィルは「殺し屋=分裂病患者」というとらえ方をしているということが理解できます。
分裂病という病自体、私の認識能力を超えるものですが、おそらくメルヴィルはこの原作本を出発点に、映画版『拳銃貸します』では充分ではなかったという殺し屋の分裂病患者としての特性と行動を踏まえつつ、そこに自分なりの解釈、視点を加え、映像表現としてより洗練された形で描こうとしたのがジェフ・コステロという殺し屋のキャラクター、そして、『サムライ』という作品であったと言えるのではないでしょうか。
また、ノンクレジットながら、一般的に『サムライ』の原作と言われているゴアン・マクレオ作『The Ronin』は、作者、書籍共にいまだ謎の存在であり、個人的にはその存在すら疑い始めています…。
フランク・タトル版『拳銃貸します』と『サムライ』の類似性、その影響につきましては、近くBLOGで取り上げる予定です。 |
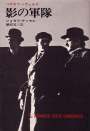
|
影の軍隊 |
ジョゼフ・ケッセル著 榊原晃三訳
早川書房 |
1970年5月に国内で出版された『影の軍隊』の原作の翻訳本。
この書物自体は、1943年に著者ジョゼフ・ケッセルがド・ゴール将軍から依頼されたのをキッカケにロンドンで書き、初版はアルジェリアで秘密出版されたとのことです。(当時、フランスはドイツの占領下で出版は許されない状況でした)
本の内容は、ドキュメンタリー・タッチのノート風小説という趣です。
マチルドの子供が何人いるとか、細かい設定が映画版と原作で異なるのはいたし方ないとして、ルイ・ノゲイラが著作『サムライ』で指摘していますように、映画版が、原作の精神に極めて誠実な映画であることがこの原作を読みますと、よく理解できます。
この本の白眉は、全体の3分の1を占める「フィリップ・ジェルビエのノート」でしょう。
本の中で紹介される抵抗運動のエピソードの数々は、ほとんどが細切れのエピソードですが、それがいかに厳しく、危険なものだったかを示す、驚くべき内容のものばかり。
そのほとんどは映画版には使われていませんが、それらをメルヴィルが撮らなかった理由は、まず映像表現として再現が困難だったためと、その一つ一つがあまりに細切れのエピソードであるため、全体のストーリーの中に組み込むのが困難だったためと思われます。
ルイ・ノゲイラ著『サムライ』でメルヴィル言うところの「原作では驚嘆すべきいいところなのに、撮影不可能なのがたくさんあるんだ」というのは、主にこれらの部分のことだと考えられます。
他に、映画版(仏語版)とは異なる原作の大きな特徴としては、次のような点が挙げられます。
●映画版ではゲシュタポ本部から脱走するジェルビエは、原作では強制収容所から脱走する。
●原作では強制収容所でのジェルビエと共産党員の若者ルグランとの関係が細かくていねいに描かれている。
●映画版ではジャン=フランソワはフェリックスを助けるためにゲシュタポに自らを売るが、原作にはそのような場面はない。
●原作にはフェリックスの家族を巡る抵抗運動にまつわる悲劇が語られている。
●原作で、ジャン=フランソワは、首領を潜水艦に案内する際に、それが兄のリュック・ジャルディだとお互いに気づき、それからレジスタンス運動を共にすることになる。
●映画版にあるロンドンでのリュック・ジャルデイのド・ゴール将軍からの勲章授与のシーンは原作にはない。
●逆に映画版の創作だと思っていたジェルビエの試射場からの脱走シーンは原作にもある。
●映画版のラストにある、残った4人のその後のエピソードは、原作本にはない。 |
| パンフレット関連 |
 |
「恐るべき子供たち」日本初公開時パンフレット |
(株)フランス映画社 |
76年に「恐るべき子供たち」が日本で初めて公開された際のパンフレット。
全12ページ(表紙含む)。
映画のあらすじ、解説、メルヴィルと原作者ジャン・コクトーのフィルモグラフィーはもちろん、この作品が75年にフランスで再上映された際にフランソワ・トリュフォーが書いた解説「最高の小説が最高の映画になった」(貴重!)、ジャン・コクトーのこの映画に対する雑感「映画『恐るべき子供たち』の即興精神」、澁澤龍彦氏の「映画『恐るべき子供たち』を見て」など、薄いパンフレットにしてはなかなか充実した内容です。 |
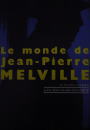 |
ジャン=ピエール・メルヴィルの世界 |
(株)ケイブルホーグ(編集・発行) |
| 89年に『賭博師ボブ』『マンハッタンの二人の男』が公開された際のパンフレット。全16ページ(表紙含む)。当然内容は上記2作品の解説がほとんどで、山田宏一氏の文章(「山田宏一のフランス映画誌」に収録されているものと同じ)、ルイ・ノゲイラによるメルヴィルへのインタビューが掲載されています。ルイ・ノゲイラのインタビュー記事は現在「サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生」で読めるものと同内容ですが、訳者が異なるせいかメルヴィルの口調の印象が随分異なって感じられます。 |
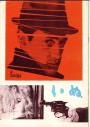 |
「いぬ」公開時パンフレット |
東和 |
ネット・オークションにて購入。
公開時のものなので、裏面の広告などもさすがに時代を感じさせ、それがまたいい味を出しています。表紙含め全12ページとちょっと薄いのが残念ですが、表紙のデザインはこの時代にしてはなかなか洒落ていると思います。
詳細なストーリーが掲載されており、誰が“いぬ”であるかが説明されているのは、“ややこしい作品”(メルヴィル談)だけにありがたいところ。
ちょうどこれが本邦初公開のメルヴィル監督作品ということもあり、彼の紹介に“ヌーヴェル・ヴァーグの父”という表現が散見されます。 |
 |
「いぬ」公開時大阪版パンフレット |
大阪映画実業社 |
この映画が日本で初公開された際の大阪版パンフレット。
東京と大阪では異なるパンフレットが作られていたとはちょっと驚きです。
ページ数は東京版と同じ12ページで、主だった解説やあらすじ等も東京版と同様であるものの、表紙も中の写真も異なるものが使用されているので貴重と言えましょう。
そして、この大阪版のみの記事として、服飾評論家の伊藤紫朗氏による「ベルモンド・コート」なるトレンチコートの解説と、キング・レコードによるこの映画の作曲者ポール・ミスラキの紹介が読めるのが貴重です。
それによると、当時、この映画でベルモンドが着ていたトレンチコートと同型の「ベルモンド・コート」なるコートが発売されたのだとか。
発売したのはどこのブランドだったのでしょう・・・。 |
 |
「ギャング」公開時パンフレット |
日本ヘラルド映画 |
ネット・オークションにて購入。
滅多に見かけないものなので、入手できてとても嬉しいです。
内容も、想像以上に解説が充実しています。
作品自体、かなりややこしいストーリーだけに(笑)、ここに記載されたあらすじは物語を理解する上で大変助かります。 |
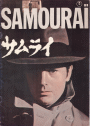 |
「サムライ」公開時パンフレット |
東宝 |
ネット・オークションにて購入。
表紙込全24ページ。
ずっと欲しかっただけに入手できて感無量です。
しかも、安かったし(笑)。
内容も期待通り、写真、解説ともに充実したもので、特に映画評論家の飯島正氏、推理小説評論家の小鷹信光氏の文章が印象的です。 |
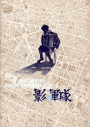 |
「影の軍隊」公開時パンフレット |
東和 |
ネット・オークションにて購入。
全24ページ(表紙含む)。
映画のあらすじ、キャストの紹介に加え、映画の背景であるレジスタンス運動について解説があるのは親切と言えるでしょう。
他に、メルヴィルの小インタビュー、メルヴィルの監督作品リスト、品田雄吉氏、山田宏一氏の解説がそれぞれ1ページずつ掲載されています。 |
 |
「仁義」公開時パンフレット |
東宝 |
古本屋にて購入。
比較的安価にて購入できました。
時代を感じさせるパンフながら、写真と解説が充実しています。
このパンフに掲載されている映画評論家・品田雄吉氏の文章を読んで、最後のヴォージェルとマテイ警視のセリフのやり取りの意味がよく分かりました。 |
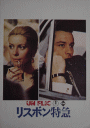 |
「リスボン特急」公開時パンフレット |
東宝 |
古本屋にて購入。
「仁義」よりも安価にて購入できました。
やはり古さは否めないものの、これも写真と解説が充実。
古本屋を探せば500円前後で見つかるかも。 |
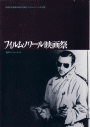 |
「フィルム・ノワール映画祭」パンフレット |
(株)ケイブルホーグ(発行) |
ネット・オークションにて購入。
88年、フレンチ・フィルム・ノワールに関連する14作品を特集上映した際のパンフレット。
全14ページ(表紙含む)。
“追悼リノ・ヴァンチュラ”と銘打っています。
メルヴィルからは「ギャング」と「リスボン特急」が上映されています。他に「筋金を入れろ」、「彼奴を殺せ」、「勝負をつけろ」、「冬の猿」、「生き残った者の掟」、「冒険者たち」、「ベラクルスの男」、「さらば友よ」、「最後のアドレス」、「蘭の肉体」、「チャオ・パンタン」、「肉体と財産」が上映されたようで、それぞれの解説が掲載されています。
それにしても、観たい作品、好きな作品が目白押し! |
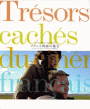 |
映画祭「フランス映画の秘宝」公式カタログ |
朝日新聞社 |
2008年東京で開催された映画祭の公式カタログ(パンフレット)。
シネマテーク・フランセーズのコレクションを中心とした計13本の希少なフランス映画が公開されたこの映画祭において、メルヴィルの長編第1作『海の沈黙』が本邦初公開されました。(2回上映)
108ページに及ぶ内容は主に次の通り。
●「13本の映画のゲーム」(セルジュ・トゥビアナ、エミリー・コキ)
●「上映作品解説」
●「崩壊ののちの豊穣―ヴィシー政権下のフランス映画一瞥」(蓮實重彦)
●「聖人よりもじかに神様に訴えるほうがいい―1940年代フランス映画の果敢な新人たち」(野崎歓)
●「現実の挑発者たち―ピアラ、ドワイヨン、ブリソー」(石橋今日美)
●各作品の監督のフィルモグラフィー
各記事ともに読み応えがありますが、とりわけ『海の沈黙』が製作された当時の状況を紹介した野崎歓氏の文章が印象的。
ちなみに、このカタログのオンライン販売はこちら |
| 雑誌関連 |
 |
キネマ旬報 1968年3月下旬号 No.463 |
キネマ旬報社 |
「サムライ」公開時のキネマ旬報。
しかし、残念ながら特集などはなく、取り上げられ方は意外なほど少なめ。モノクロ2ページのグラビアと、岡田晋氏による「旬報試写室」、「外国映画紹介」に略筋が載っている程度。
しかし、「旬報試写室」において岡田氏は、この映画の冒頭部分を観ただけで学生時代にルネ・クレールの映画を観た時のような映画ファン的心情をくすぐられ胸が熱くなったと語り、この映画は「一種のドキュメンタリー」であり、「ドラマのツボを押さえながら、ツボをはずしたところに、ぼくの心をとらえる映画なるものの面白さ」があり、「不必要なほど細かい各シーンのディテールに、ドラマの計算をこえた映画なるものの魅力がかくされている」と書いています。
そして、「アラン・ドロンは、近頃の主演映画中、最高の出来、アンリ・ドカエの色彩撮影は、まことに見事、フランソワ・ド・ルーベの音楽は好みにピッタリ」と書くなど、大変気に入られたご様子。 |
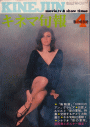 |
キネマ旬報 1970年春の特別号 No.520 |
キネマ旬報社 |
「巨匠メルビルと『影の軍隊』特集」と表紙に銘打った「影の軍隊」公開前のキネマ旬報。
「ジャン・ピエール・メルビル監督研究」と銘打った特集は、「『影の軍隊』とジャン・ピエール・メルビルとレジスタンスをめぐる映画的討論」という総勢7人による8ページにわたる特別座談会、「アメリカ映画を父としレジスタンス体験を母として」という田山力哉氏のメルヴィル論、そして、同じく田山力哉氏訳・編による「J・P・メルビル+その他の人びと その全作品を語る」というメルヴィル本人らの言葉による簡単なフィルモグラフィという3部構成。
5ページにわたるモノクロ・グラビアにもメルヴィル本人を始め、ゴダール、コクトーらによるメルヴィルについての語録を掲載。
おそらく日本の映画雑誌でここまで大々的にメルヴィルが取り上げられたのは初めてだったでしょう、このグラビアのタイトルが“未知の巨匠ジャン・ピエール・メルビル”となっているのが当時の受容状況を表していて面白いと思います。
余談ですが、表紙のジャクリーン・ビセットが美しい!(笑) |
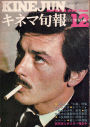 |
キネマ旬報 1970年12月下旬号 No.538 |
キネマ旬報社 |
「メルビル『仁義』特集とシナリオ」と表紙に銘打った「仁義」公開前のキネマ旬報。
5ページにわたるモノクロ・グラビア、「『仁義』とジャン・ピエール・メルビル監督とその映像の精神主義」と銘打った池波正太郎、菊村到、品田雄吉、河原畑寧各氏(司会・白井佳夫)による7ページにわたる特別ディスカッション、そして三木宮彦氏採録による「仁義」シナリオ収録という大変な取り上げられぶりです。
これは、いかに当時、メルヴィル、そして「仁義」が映画ファンに注目されていたかを表しているのではないでしょうか。
事実、ここに収録されたディスカッションは、パリで当時メルヴィルに会った河原畑氏を中心に、メルヴィル作品の面白い点、不満な点を客観的に論じているのが読んでいて大変興味深い。
「仁義」のシナリオもこの作品を理解する上で大きな助けとなります。
それにしても・・・このシナリオでは、なぜ故買屋が関西弁なんだ!?(笑) |
 |
キネマ旬報 1972年12月下旬号 No.595 |
キネマ旬報社 |
「『リスボン特急』とシナリオ」と表紙に銘打った「リスボン特急」公開時のキネマ旬報。
その内容は、4ページのモノクロ・グラビア、それぞれ3ページずつの「『リスボン特急』の映画的魅力」と題する白井佳夫氏、「『リスボン特急』とメルビル監督」と題する田山力哉氏の評論、そして、三木宮彦氏採録による「リスボン特急」シナリオという構成。
白井氏、田山氏の評論がそれぞれメルヴィル作品の本質を突いていて出色といってよく、特に田山氏は「リスボン特急」編集中のメルヴィルに直接話を聞いているだけに貴重。
それによると、「リスボン特急」の編集にメルヴィルは8ヶ月も掛けたらしく、本当に身を削りながら作品を完成させたのがよく分かり、それから約1年後に心臓発作で亡くなってしまったのも頷けなくはありません。 |
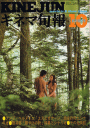 |
キネマ旬報 1973年秋の特別号 No.615 |
キネマ旬報社 |
メルヴィルの訃報を伝えるキネマ旬報。
ここでは特に特集などは組まれておらず、巻頭の「随想」に清水馨氏(東和渉外宣伝部宣伝部長)の文章「サムライ・メルビルの訃」があるのみ。分量も1ページちょっとと、これ以前に『影の軍隊』『仁義』『リスボン特急』と大きく特集を組まれていたことを思うと寂しい気がします。(ちなみに、キネマ旬報には山田宏一氏による追悼記事が、後の616号、617号に掲載されます)
しかし、生前のメルヴィルに一度会ったことがあるという清水氏の文章は短いながらも大変面白く、大資本の要請に応えようとしなかったメルヴィルに対するプロデューサーのロベール・ドルフマンの非難を取り上げつつ、ずっと一人で映画を作り続けたメルヴィルのかたくなな変人ぶりを好意的に紹介しています。
その中から・・・
「彼の作品における男の精神のきびしさ……。画面におけるカラーの鋭さ……。それが、やはり、彼のナマの生活に見てとれるのだ。」・・・
「サムライは、その最後に散らねばならぬ。あれはちょっと、太りすぎだったよ、などというコメントはこの際、ともかくとして、何とも、この西洋侍は早めに散ってしまったことか。」・・・ |
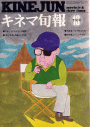 |
キネマ旬報 1973年10月下旬号 No.616 |
キネマ旬報社 |
前号の訃報に続く、メルヴィル追悼号。
とはいえ、関連記事は山田宏一氏の「シネ・ブラボー」のみなのがちょっと寂しい。
「ジャン=ピエール・メルヴィル追悼(1)」と銘打ったその記事は全6ページに渡ってメルヴィルの全作品のフィルモグラフィを紹介するもの。
もともとはユニフランス・フィルム駐日代表部発行のフランス映画の会報「ユニフランス・フィルム」のメルヴィル追悼号のために準備されたものなのだというその内容は、作品のデータ、スタッフ、キャストの名称などの紹介。
全作品を網羅したその情報は現在でも貴重極まりなく、当然、このサイトでもFILMOGRAPHYの作品紹介のページを中心に参考にさせていただいております。 |
 |
キネマ旬報 1973年11月上旬号 No.617 |
キネマ旬報社 |
前号に引き続き、山田宏一氏の連載「シネ・ブラボー」において、「ジャン=ピエール・メルヴィル追悼(2)」として「ジャン=ピエール・メルヴィルのフィルモグラフィについての覚え書」というタイトルでメルヴィルを論じた文章が掲載されています(4ページ)。
メルヴィルへの思いに溢れたその文章は(批判も含め)読む者を惹き付ける魅力に満ちています。
中からいくつか抜粋して紹介します。
「ぼくは、まず、日本で『いぬ』を見て、メルヴィルのフィルム・ノワールの感触にしびれてしまい、その後、パリのシャイヨー宮のシネマテークで、メルヴィル特集があったときに、連日通いつめて、日本未公開の作品もいくつか見ることができたのだった。」
「ぼくは、アラン・ドロンとともにジャン=ピエール・メルヴィルの暗黒映画は、色彩を加味したけれども、ユーモアを失って堕落したと思いこんでいる」
「こんなにすばらしい、イキな、キザな、男の死にっぷりは、どんなにすぐれたアメリカのB級ギャング映画にだってなかった―と思われるくらい、この『いぬ』のラスト・シーンのカッコよさに、ぼくは完全にしびれてしまったのだった。」
「帽子は、メルヴィルのクールで非情な暗黒映画の世界においては、唯一の男のやさしさの表現であると同時に、男のいのちであり、存在そのもののアイデンティティですらあるのだ。」
「あのステュディオ・ジェンネルの全焼による心の痛手と絶望は深かったにちがいない。なにしろ、このスタジオは映画作家メルヴィルにとって、自由と独立の象徴である彼ひとりの牙城だったのだ。それが灰塵と化したときの彼の絶望を想像するのは、そんなにむずかしくない。思うに、ジャン=ピエール・メルヴィルは、このとき、すでに、1度死んでしまったのである。かくて、夢の牙城ステュディオ・ジェンネルの全焼のあと、メルヴィルは、アラン・ドロンとの出会いによって、すなわちコマーシャリズムの磁場に身を捨てることによって、『サムライ』とともにふたたび甦ったのだ。たぶん、それ以外に立ち直る方法はなかったにちがいない。」(引用注―ステュディオ・ジェンネルの全焼は『サムライ』の撮影の途中の出来事でした。)
「ジャン=ピエール・メルヴィルは夜と雨の映画作家である。」 |
 |
世界の映画作家18 犯罪・暗黒映画の名手たち |
キネマ旬報社 |
73年発売のキネマ旬報の別冊。
ジョン・ヒューストン、ドン・シーゲル、そしてメルヴィルを中心とした、タイトル通り犯罪・暗黒映画そのものの特集号。
神保町の古本屋で見つけましたが、あまり出回っていないせいか、3000円もしました(笑)。
メルヴィルの記事は期待したほどは多くないものの、70年、72年と二度メルヴィル邸を訪問した河原畑寧氏による記事「メルヴィルの世界」を読めるのがとにかく貴重。
他にも双葉十三郎氏による「アメリカ犯罪・暗黒映画の系譜」など読み応えのある記事が満載。
状態のキレイなものが安く売られていたら、ファンなら是非手に入れたいところ。 |
|
|
映画秘宝 2009年 02月号 |
洋泉社 |
アラン・コルノー監督の『マルセイユの決着(おとしまえ)』の公開を記念して、昨今の映画雑誌には珍しく7ページのフィルム・ノワール特集が組まれています。
フィルム・ノワールといっても、アメリカのそれではなく、あくまでもフレンチ・フィルム・ノワールの特集である点が嬉しい。
内容は、『マルセイユの決着』の解説、『フィルム・ノワールの作り手たち』と題したメルヴィルとジョゼ・ジョヴァンニの紹介、『フィルム・ノワールの男たち』と題したギャバン、ドロン、ベルモンド、ヴァンチュラ、モンタン、トランティニャンの紹介、そして、『フレンチ・フィルム・ノワール傑作選20!』と題したメルヴィルの『いぬ』『サムライ』『仁義』『リスボン特急』他20作品の名作の紹介、『現代フィルム・ノワールの作家たち』等々。
『サムライ』がメルヴィル初のカラー作品と紹介されたり(メルヴィル初のカラー作品は『フェルショー家の長男』)、『仁義』の作品詳細が『さらば友よ』のそれになっているなど、編集に荒さも目に付きますが、80年代の珍しい作品も紹介されるなど、なかなか読み応えがある内容となっています。 |