| �X�^�b�t |
| ����F |
�R���i�i�p��/���[�}�j Films Corona(Paris/Roma) |
| �����\�F |
���x�[���E�h���t�}�� Robert Dorfmann |
| �����C�F |
�s�G�[���E�T��=�u�����J Pierre Saint-Blancat |
| ���āE�r�{�E�䎌�E�ēF |
�W����=�s�G�[���E�������B�� Jean-Pierre Melville |
| �ē�F |
�W����=�t�����\���E�h���� Jean-François Delon |
| ���ēF |
�}���N�E�O�����k�{�[�� Marc Grunebaum |
| ���F |
�s�G�[���E�^�` Pierre Tati |
| �B�e�ēF |
���@���e���i�����^�[�j�E�E�H�e�B�b�c Walter Wottitz |
| �J�����E�I�y���[�^�[�F |
�A���h���E�h�}�[�W�� André Domage |
| �B�e����F |
���@�����[�E�C���@�k�[ Valéry Ivanow |
| �i�s�F |
�W�����E�h���[���� Jean Drouin |
| ���F |
�t�B���b�v�E�P�j�[ Phillip Kenny |
| �ҏW�F |
�p�g���V�A�E�l�j�[ Patricia Nény |
| �ҏW����F |
�}���[=�W���[�E�I�f�C�A�[�� Marie-José Audiard |
| ���F |
�\�t�B�E�^�` Sophie Tati |
| ���p�F |
�e�I����[���b�X Théo Meurisse |
| ���p����F |
�G�����P�E�\�m�C�X Enrique Sondis |
| ���u�F |
�s�G�[���E�V������ Pierre Charron |
| �����F |
���l�E�A���u�[�Y René Albouze |
| �ߑ��F |
�R���b�g�E�{�[�h Colette Baudot |
| �J�g���[�k�E�h�k�[���̍����h���X�F |
�C���E�T���E���[���� Yves Saint-Laurent |
| �є�F |
�W�����k�E�i�^�t Jeanne Nataf |
| �L�^�F |
�t�������X�E�����R���W�F Florence Moncorgé |
| �^���i�����j�F |
�A���h���E�G�����F�[ André Hervée |
| �T�E���h�ҏW�F |
���[���X�E���[�}�� Maurice Laumain |
| ���y�F |
�~�V�F���E�R�����r�G Michel Colombier |
| �^���F |
�W�����E�l�j�[ Jean Neny |
| �G���f�B���O�E�e�[�}�i�́j�F |
�C�U�x���E�I�[�u�� Isabelle Aubret �u�����N����悤���v |
| �G���f�B���O�E�e�[�}�i�쎌�j�F |
�V�������E�A�Y�i�u�[�� Charles Aznavour
Chacun de nous est seul sur l'autre rive
Du fleuve trouble des passions
Pour voir partir à la dérive
Ses illusions
Adieu ce qui fut nous
Vive que vive
Le destin a tiré un trait
C'est ainsi que les choses arrivent
Arrivent
Voici venir le temps des regrets
�ǓƂ݂̊ɂ�������
�Ƃ�v���Y�ގ�
����ɐg���܂��������Ȃ�
�܂�Ȃ����z�ɂ͂��悤�Ȃ�
�^���̂��������
�l�̈����݂�m�������Ȃ�
���́@�Ƃ����̎�
|
| �f��`���̃G�s�O���t�F |
�gLes seuls sentiments que l'homme ait jamais été capable
d'inspirer au policier sont l'ambiguïté et la dérision...�h
�@�@François-Eugène Vidocq
�Y�����l�Ԃɕ�������͋^���ƚ}�肾���ł���c
�@�@�t�����\��=���W�F�[�k�E���B�h�b�N |

|
| �L���X�g |
| �G�h�D�A�[���E�R�[���}�� Édouard Coleman�F |
�A�����E�h���� Alain Delon |
| �J�e�B Cathy�F |
�J�g���[�k�E�h�k�[�� Catherine Deneuve |
| �V���� Simon�F |
���`���[�h�E�N�����i Richard Crenna |
| �|�[���E�E�F�x�� Paul Weber�F |
���J���h�E�N�b�`���[�� Riccardo Cucciolla |
| �|�[���̍� sa femme�F |
�V���[�k�E���@���[�� Simone Valère |
| �������҂̐a�m�F |
�W�����E�h�T�C Jean Desailly |
| ������ Morand�F |
�|�[���E�N���[�V�F Paul Crauchet |
| ���C�E�R�X�^ Louis Costa�F |
�}�C�P���E�R�����b�h Michael Conrad |
| �}���N�E�A���v�C Marc Albouis�F |
�A���h���E�v�b�X André Pousse |
| �M���r�[�F |
���@�����[��E�B���\�� Valérie Wilson |
| �^�щ��}�`���[ Mathieu la valise�F |
���I���E�~�j�X�j Léon Minisini |
| ��s�̏o�[�W�F |
���W�F�E�t���f Roger Fradet |
| �a�@�̎�t�W�F |
�J�g���[�k�E���e�B Catherine Rethi |
| ��s���F |
�s�G�[���E���H�f�B�G Pierre Vaudier |
| �^�щ��ɖ����n���M�����O�F |
�W����=�s�G�[���E�|�W�F Jean-Pierre Posier |
| ���F |
�W���b�N�E������ Jacques Leroy |
| ���̏o���ҁF |
�A�����E�}���g�[ Henri Marteau�A���C�E�O�����f�B�f�B�G Louis Grandidier�A�t�B���b�v�E�K�X�e Philippe
Gasté�A�h�~�j�N�E�U���^�[�� Dominique Zentar�A�W���R�E�~�J Jako Mica�A�W���[�E�^�t�@�l�b�� Jo
Tafanelli�A�X�^���E�f�B���N Stan Dylik�A�W�����W���E�t�����A�� Georges Florian�@�� |
|
| �R�_�b�N�E�C�[�X�g�}���E�J���[ |
| 105���B�z�� �� �R���i�E�t�B���� |
| �p���A���@���f�݁iVendee coast�j�ɂă��P�B�e�A�y�уu�[���[�j���B�e���ɂăZ�b�g�B�e�B |
| �p�����J �� 1972�N10��25�� |
| ���{���J �� 1972�N12��16���B�z�������a |
| ������DVD����B����VHS�r�f�I�����^������B�C�O��DVD����BDVD���������� |
|
�Ȃ��A�X�^�b�t��L���X�g���̃f�[�^�Ɋւ��܂��ẮA����u�T�����C�v�i���C�E�m�Q�C�����A���^���A�����Њ��j�A�u�L�l�}�{��@1973�@��616�v�i�V�l�E�u���{�[�@�W����=�s�G�[���E�������B���Ǔ��i1�j�R�c�G��j�A�uJean-Pierre Melville/An American in Paris�v�iGinette Vincendeau���j��3�����Q�l�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B
�܂��A�X�^�b�t�̖�E�����A�f��{�҂̃G���h�N���W�b�g�Ƃ͑����\�L���قȂ�Ǝv���镔�����������܂��B |

|
| ���r���[ |
����́wUn Flic�x�Ƃ́u�Y���v�i�f�J�j�̈ӁB
�W����=�s�G�[���E�������B���ē̃I���W�i���r�{�ɂ���i�ł���A�M��́w���X�{�����}�x�Ƃ́A�f��̌�����̈�ł����ԓ������V�[���̕��䂪���X�{���s���̓��}�Ƃ������Ƃł����āA�X�g�[���[�S�̂̒��ł͂��قǏd�v�ȈӖ��̂���^�C�g���Ƃ͌����܂���B
����̒���ł͓����悤�ȖM��̉f�悪���ɂ����邽�߂ɁA���̂悤�ȖM���t�����̂��Ǝv���܂��B
���ʓI�ɁA�������B���ē̈��ƂȂ��Ă��܂��܂������A���̍�i�́A�Â��́w�q���t�{�u�x�A�w���ʁx����w�M�����O�x�A�w�T�����C�x�A�w�m�`�x�Ɏ���܂ŁA�������B�������ӂƂ��Ă����uPolice
Thriller�v�A�܂�A�ƍߎ҂ƌx�@�A�Y���̊Ԃ̊�����ߌ���`������i�Q�̌n���Ɉʒu�����i�ł���Ɠ����ɁA�w�T�����C�x�A�w�m�`�x�Ƒ������A�����E�h�����剉3����̍Ō�ƂȂ�����i�ł�����܂��B
���̉f��́A�������E�ō��̔��j�����ł������A�����E�h�����ƃJ�g���[�k�E�h�k�[���̏��������Ȃ�Ƃ����Ă��ő�̘b��ŁA���J�����A���{�ł����Ȃ�̃q�b�g���L�^�����Ƃ̂��ƁB
���̓�l�̋����́A��Ɂw�Ō�̕W�I�x�i82�N�B�ēF���o���E�_�r�[�j�����邭�炢�ŁA��l�̃L�����A�̒������l����A��ϒ��������Ƃƌ�����ł��傤�B
����ȑO�Ɂw�T�����C�x�A�w�m�`�x�Ɏ剉�A�Ƃ�킯�O��w�m�`�x�ŋ��s�I�ɂ��听�������߂Ă����h�����̍���ւ̏o���͓��R�Ƃ��Ă��A����܂Ń������B���ƑS���ړ_�̂Ȃ������h�k�[���̏o���́A�����Ƃ��Ă����Ȃ�ӊO�Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��X�^�[��l���������������E�V�[�������蕨�̈�ƂȂ������̍�i�́A����䂦�ɂ��A�ȑO�̃������B����i�ɔ�ׂ�Ɠ����̃t�����X�f��炵���I�V�����i�H�j�ȃ��[�h���Z���i����̓G���f�B���O�̃C�U�x���E�I�[�u���̉̂ɂ������j�A�ȑO�̃������B����i���L�̃h���C�ȃ^�b�`�͂��Ȃ蔖�܂��Ă��܂��B
�ϋq�����̖ʂł́A�ُ�Ȃ܂ł̃q�b�g���L�^�����w�m�`�x�ɂ͋y�Ȃ����̂́A�{���t�����X�ł����������̃q�b�g�������悤�ł��̂ŁA���s�I�Ɏ��s�ɏI������킯�ł͂���܂��A���J�������A�����Č��݂��A���̍�i�ւ̕]���͌����č����Ƃ͌����܂���B

��N�A�A�����E�h�������g�A�u�w���X�{�����}�x�͒��r���[�Ȏ��s��ɂȂ��Ă��܂����v�Ƃ����悤�Ȍ��t���c���Ă��܂����A���l�̕]�����A���̃������B���̌���ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ藎�����i�ł���Ƃ������̂ł��B
�������A�������B���ē�i�ł�����A���ɂ͂Ȃ����͓I�ȉf��ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��A��������������Ă��A���̃������B����i�Ɣ�ׂ�ƕ]�����������Ȃ��Ă��܂��܂��B
���̗��R�͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤���B
���l�̈ӌ��ł����A���̑傫�ȗ��R�̈�́A�h�����ƃN�����i�̊W�A�܂�͓�l�̒j�̗F��W�ɁA�ς�҂ɑi�������邾���̐����͂���������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�f��������ɂȂ�Ε�����܂����A��l�̌��݁A�����ĉߋ��̊W�����A�f��̒��ŁA���t�Ƃ��Ă��A�܂��f���Ƃ��Ă��A�ϋq���[���ɔ[�������邾���̐������قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ��̂ł��B
�������A��l���F�l�ł��邱�Ƃ͉f����ςĂ���Ε�����܂��B
�������A�����炭�͐[���F��Ō���Ă���̂ł��낤��l���A�Ȃ����݁A�Y���ƃM�����O�Ƃ��������̗���ɒu����Ă���̂��A�����āA���̗���̈Ⴂ������Ȃ���A��l�����ѕt���Ă���͈̂�̉��ł���̂��c�����̓_���[���ɐ�������ɑ�����̂��f��Ɍ���I�ɕs�����Ă��邽�߂ɁA��l�̊W�̐^�ӁA�h�k�[��������O�p�W�̔������A�����āA���X�g�̏e���̈Ӗ��������A�ϋq�ɏ[���ɓ`��肫��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B
��l�̓��W�X�^���X�̓��u�������Ƃ̐�������܂����A����̐ݒ��͂����炭�����Ȃ̂ł��傤���A�f����ς����ł́A���̂��Ƃ��ϋq�ɗ��������邾���̐���������܂���B
�{���ł���A�����������ߋ����܂߂���l�̐[���W���ϋq�ɓ��S�����邾���̉��炩�̃G�s�\�[�h������ɕK�v�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������A�������B����i������܂ł����ɂȂ��Ă�����Ȃ�A�����������l�ԊW�̑�_�ȏȗ��̓������B���̏퓅��i�ł͂Ȃ����A�Ǝv������������Ǝv���܂��B
���R�A�������B���́A���̍�i�ɂ����Ă��m�M�ƓI�ɂ����Ă������Ă���̂ł��傤���A����ȑO�̍�i�ł́A���Ƃ��l�ԊW�̐����̏ȗ����Ȃ���Ă��Ă��A��������ė]�肠��悤�ȈӖ��[���`�ʂ��ǂ����ɂ�����Ɨp�ӂ���Ă���A�����Ă��̏ȗ����f��I�Ȍ��_�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B
�Ƃ��낪�A���̍�i�ł́A�ȗ���₤�ׂ��`�ʂ��[���ɗp�ӂ���Ă��炸�A���ʓI�ɁA�ȗ������̂܂܉f��I���_�ƂȂ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̂��Ƃ́A���̉f��̃��X�g�E�V�[���ɂ��傫�ȉe�𗎂Ƃ��Ă��܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�܂��A���̍�i�̃��X�g�E�V�[���������ɂȂ�A���ꂪ�w�T�����C�x�̃��X�g�E�V�[���̏Ă������ł��邱�Ƃ������ɂ���������������ł��傤�B
�������A�Ă��������̂��̂������Ƃ������Ƃł͌����ĂȂ��̂ł����A���ꂪ�ǂꂾ���f��Ƃ��Ă̐����͂������Ă��邩�ۂ������ł��B
�w�T�����C�x�̏ꍇ�A�A�����E�h����������W�F�t�E�R�X�e���������Čx�@�̏e�e���郉�X�g�V�[���ɂ́A�����Ȃ��đR��ׂ��A�Ƃł������悤�ȁA�����̉^���_�I�Ȑ����͂�����܂����B
����́A�w�T�����C�x�Ƃ����f����n�߂���ςĂ���A���X�g�ł��������W�J�ɂȂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��A�Ɗϋq�ɔ[�������邾���̉f��I�Ȑ����͂��������킹�Ă����Ƃ������Ƃł��B
�Ƃ��낪�A�w���X�{�����}�x�̏ꍇ�A�N�����i�����e���������Ă���ӂ�����Ă܂ŁA�h�����̏e�����Ă��܂����R���悭������܂���B
����A������Ȃ��͂Ȃ��̂ł����A���̐����͂��f��I�ɂ����ɂ��ア�̂ł��B
�h�����ɏe���������A�S�Ă��ϔO�����N�����i���A�F�l�ł���h�����̏e���������Ď�A���̂��Ƃ��ϋq���[������ɂ́A��͂�A����܂ł̓W�J�ɂ����āA��l�̊Ԃ̐[���F�������������A�Ȃ�炩�̌���I�A�Ȃ����f���I���������������K�v�������Ǝ��͎v���܂��B
�M������o�b�N�ɁA�h�����̃A�b�v�����X�Ɖf���o���G���h�N���W�b�g���A���ǁA���̓�l�̊W�̈Ӗ��������`��肫���Ă��Ȃ��܂܂��̃V�[���ւƗ���Ă䂭���߁A�h�����̓܂����\��Ɋϋq��������d�ˍ��킹�邱�Ƃ��o���ʂ܂܃G���h���[���ƂȂ��Ă��܂��̂ł��B
�t��������A�h�����̊���A�b�v�̂܂ʂ������邱�̃G���h�N���W�b�g�̉f�����A�������B���̉f���Ƃ��Ă͂��܂�ɐ^�����߂��āA�|�������߂��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�����������܂��B
���ɂ��A�������B����i�ł������͓I�ȃi�C�g�N���u�̃V�[�����A���̍�i�ł̓n�b�L�������Ė��͂��������܂���B
���ɁA�_���T�[�̈�l���h�����Ɍ������Ď��U��A����Ƀh������������V�[���Ɏ����ẮA�������B���炵����ʑ����ۂ��ŁA�ڂ��^���Ă��܂��܂��B
�f��̑傫�Ȍ�����̈�ł���A�N�����i�ɂ���ԓ������V�[�����A��Ԃɏ�荞��ł���̒��ւ��A���U���̃V�[����O�O�ɕ`�ʂ���ȂǁA�������ɖ����Ă���܂����A20���̐������Ԃ܂Ő݂��ă��A���E�^�C���ł����Ղ�`���Ă��銄�ɂ́A���̖���肻�̂��̂��f��̃X�g�[���[�̃o�����X���猾���Ă���قǑ傫�ȈӖ�������킯�ł��Ȃ��A�T�X�y���X�̂��߂̃T�X�y���X�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ�����ۂ������ł��B
�����A�悭�w�E�����A�~�j�`���A�̗�Ԃƃw���R�v�^�[�̖͌^�����̃V�[���Ŏg���Ă���_�ɂ́A���l�͂�������s���������܂���B
���̂��Ƃɉ����A���[�������p�ق̃V�[���̃o�b�N����������ł��邱�Ƃ��A���C�E�m�Q�C�����w�T�����C�x�̉���玁�Ɩ��r�F���̑Βk�ł��w�E����Ă��܂����A�����������ʂł̃��A���Y���ɂ̓������B���Ƃ����f��ē͂��������������������Ȃ��l�������Ǝ��͊����Ă��܂��B
�Ⴆ�A�~�j�`���A�͌^�͂���ȑO�́w�e�̌R���x�A�w�t�F���V���[�Ƃ̒��j�x�ł��A���ꂼ���s�@�̃V�[���Ŏg���Ă���܂��B
���Ƃ��ƃX�N���[���E�v���Z�X�𑽗p����ēł��邱�Ƃ�����A�f���I�ɃV�[���̈Ӗ����`���A�]�v�Ȃ����͊|���Ȃ��Ƃ����̂��������B���̃|���V�[�������悤�ɂ��v���܂��B�i���ہA�ǂ����ŁA���̂��Ƃ��w�E���ꂽ�ہA�u����Ȃ��Ƃ���������A�q�b�`�R�b�N�͂ǂ��Ȃ�H�v�ƊJ�������Ă����ƋL�����Ă��܂��B�j
�����̂��Ƃ́A�����̃��A���e�B����A�N�V�����f��������ꂽ�ڂɂ͑傫�ȕs���ƂȂ肦�邩������܂��A���̉f��̌��_�́A��ɋ������悤�ȁA�����Ƒ��̖ʂɂ���Ƃ����̂����̍l���ł��B
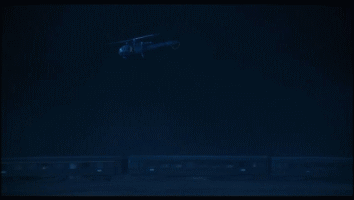
�ȏ�A���낢��ᔻ�߂������Ƃ������Ȃ菑���A�˂Ă��܂��A���̉f��̃t�@���̕��ɂ͑�ϐ\����Ȃ��̂ł����A���R�̂��ƂȂ���A���̍�i�Ȃ�ł͂̑f���炵�����͂����邱�Ƃ������܂ł��Ȃ����Ƃł��B�i���������Ƃ����܂��A����������̉f��̃t�@���̈�l�ł��j
���̉f��Ȃ�ł͂̓��F�������������Ă݂܂��傤�B
�܂��A���̍�i�̓��F���ꌾ�Ō����Ȃ�A�g�o��l���̎����ɓO�ꂵ�Ă���������f��h�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�Z���t��i���[�V���������A���������������̐S����Ԃ�Y�قɕ�����Ă���f��Ȃ̂ł��B
�������A���̌X���̓������B���̂���ȑO�̍�i�ɂ�����܂������A�����܂œO��͂��Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ł���ۓI�ȃ����V�[���������܂��ƁA�`���̋�s�����̏�ʂł��B
��ɃN�����i�A�v�b�X���Ԃ���~��A��s�ɓ���܂��B
���̏��Ԃ̓N�b�`���[���ł��B
�������A�ނɂ͑���3�l�̂悤�ȕ��̐�������x���͂���܂���B
��ɕ����邱�Ƃł����A�ނ̓��X�g�����ꂽ����s���ŁA�������ʂ̉ƒ�l�Ȃ̂ł��B
��s���ŃN�b�`���[����҂��Ȃ���A�u�x���c�B�A�C�c�A���v���H�c�v�Ƃł������悤�ȃN�����i�ƃv�b�X�̕s�����Ȏ������������܂��B
���ꂩ��A�ԓ��̃N�b�`���[���̉����ɋ������悤�Ȏ����A�N�b�`���[���𑣂��R�����b�h�̈Ј������鎋���ƁA4�l�̎����̓������܂�ň�l�̐l�Ԃ̎����̂悤�ɓ����悤�ȑ����Ŏ��X�Ɖf���o����A�N�b�`���[�����ӂ������ĎԂ���ɂ���c���̊ԁA�ق�̐��b�Ȃ̂ł����A���̉f���̗��ꂪ�▭�Ƃ��������悤�̂Ȃ��قnj����Ȃ̂ł��B

�����āA���̖`���̋�s�����̃V�[���́A�l�Ԗ��Ȃ��ނ������@�I�ȃ}���V�����̌����A�C�݂̍r�X�����g�A���������̒������̎Ԃ���������s�ւƌ������`�ʂȂǁA�w���X�{�����}�x�S�т̒��ł��ł��ْ���������A�ς�҂ɗ₦�₦�Ƃ����f���̊��G�����̂܂ܓ`��邩�̂悤�ȑf���炵���o���h���ƂȂ��Ă��܂��B
�����A�w���X�{�����}�x�B�e��̃������B���ɒ��ډ�����c�R�͍Ǝ��ɂ��A�������B���̓o�b�N�̔g�̉��ɂ��O��I�ɂ������A�C�̔g���ʂ��������E�J�b�g�̂��߂�15�{���̘^���e�[�v����点���Ƃ̂��Ƃł��B
�g�����ɂ���������f��h���Ɛ�ɏq�ׂ܂������A�o��l���̎����������ɂ��Ӗ����肰�ɉf���o����Ă����ʂ͑��ɂ���������܂��B
�ꕔ�ł����A���̗�������Ă݂܂��傤�B
��s���̃N�����i�ƃv�b�X�̔w���ɒ�������s���̌x���S�̂��鎋���B
�E���ꂽ���t�w�\��Ō��߂�h�����̎����B
�Ⴂ�j�������������Ɍ��߂铯�����҃h�T�C�̎����B
�ԓ��Ńh���������߂�I�J�}�i�H�j�̏�̂Ȃ܂߂����������B
�g�d���h���玩��ɖ߂��ċ��̒��̎����̎p�����߂�N�b�`���[���̎����B
�i�C�g�N���u�Ńs�A�m��e���h���������߂�h�k�[���̎����B
�����āA���̓�l�̎p�����߂�N�����i�̎����B
���[�����ŃS�b�z�̊G�����߂�N�����i�̌����������B
�a�@�Ŕ��������̃v�b�X����C���˂Ő▽������ۂ̃h�k�[���̎����B
�R�̏���͂܂����ƃh�����ɑł��ꂽ��A�h���������߂�I�J�}�̏�̍��߂������Ȏ����B
�����āA�R�����b�h���x�@�ɘA�s������́A�R�����b�h�̕s�G�Ȏ����ƁA���\��ȃh�����̎����̖����̑Ό��B
�R�����b�h��q�₵����A�N�����i�̃i�C�g�N���u�ŃN�����i�Ɂu���c�͓f�����v�ƙꂢ����̃h�����̎����A�����āA������~�߂�N�����i�̎����B
�����āA���X�g�V�[���Ō�������h�����ƃh�k�[���̎����A�����ăG���f�B���O�ŊM������o�b�N�ɃA�b�v�ɂȂ����h�����̎����c�B
�����āA�g�����h�Ƃ����A�����炭���̉f��ň�ԗL���Ȃ̂��A�h�����A�h�k�[���A�N�����i3�l�̎�������������i�C�g�N���u�ł̃V�[���ł����A�l�I�ɂ̓h���������߂�h�k�[���̎��������܂�ɐ��X���߂���悤�Ɋ����A���������āA���̃V�[���͐��Ɍ����Ă���قǂɂ͐������Ă���Ƃ͎v���܂���B
�������A������ɂ���A���̍�i�́A�����őS�Ă�����Ă��܂����Ƃ������̔@���A�l���̎����ɓO�ꂵ�Ă����������i�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
���̎��݂��S�Đ������Ă���Ƃ͌����Ȃ���������܂��A�����ɋ���Ȃ܂ł̍�Ɛ��������邱�Ƃ��܂��m���Ȃ̂ł��B

����ƁA�C�O��DVD���ςď��߂ĕ����������Ƃł����A���̍�i�́g�������B���E�u���[�h�ɂ�肱��������f�����𖡂킦���i�ŁA���̓O��Ԃ�ɂ͖{���ɋ����قǂł��B
���̂�����̃j���A���X�͎c�O�Ȃ��烌���^���E�r�f�I�Ȃǂł͂悭�`���܂���̂ŁA������DVD���悤�₭�o�����Ƃł����A����Ƃ�DVD�Ŗ�����Ă������������Ǝv���܂��B
���̍�i�̎B�e�ḗA���N�̖��F�A�����E�h�J�ł͂Ȃ��A�ߋ��Ɂw�j��ő�̍��x�i62�N�j�̎B�e��S�����A�A�J�f�~�[�B�e�܂���܂����啨�L�������}���A�����^�[�E�E�H�e�B�b�c�i���@���e���E���H�e�B�b�c�j�ł��B
�E�H�e�B�b�c�́A�������B���́w�e�̌R���x�ł������E�̓���B�e��S�����Ă���A���́w���X�{�����}�x�ɂ����ẮA�������B���̈ӌ��f���������Ȏd�����s�����ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��A�~�V�F���E�R�����r�G�̌��ʉ��̂悤�ɗ₽���������y���A�u���[�̉f���ɑ�ς悭�����Ă��܂��B
�L���X�g�͂ǂ��ł��傤���B
�w�T�����C�x�w�m�`�x�ɑ����āA���ꂪ3��ڂ̃������B����i�剉�ƂȂ�A�����E�h�����́A�����ŃL�����A�j�㏉�߂Ă̌Y�����������Ă��܂��B
���̍�i�ŁA�h�����ɖ���U��ɓ�����A�������B���͌Y�����A�ƍߎҖ��i�V�����j�̂ǂ����I��ł��悢�ƃh�����ɓ`�����炵���̂ł����A�h�����͋r�{��ǂ�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Ɗ����Ȗ��̓V�����̕����Ɗ������A�ƍߎҖ��͂���܂ʼn��x�������Ă����̂ŁA�����ČY��������]�����̂������ł��B
���̌Y�������A���肫����̐��`���Ɉ�ꂽ�P�l�ł͂Ȃ��A�ނȂ�ł͂̌�������������̋����Y������ł��o���Ă���̂���ۓI�ł��B

�����h�������݂ōD���ȃV�[���́A���X�g�����ŃR�����b�h��ߕ߁A�I�t�B�X�Őq�₷��܂ł̈�A�̃V�[���ł��B
�ߕ߂̃V�[���ł́A�d�b�ŌĂяo���ꂽ�q�ɕ������h�������A�����ނ�Ɍ��ɗ����ăR�����b�h�ɕ������ē|���V�[���́g�C�L�h�������ł����A�I�t�B�X�ɃR�����b�h��A�s������A���\��A�����̃v���b�V���[�������A���e����e�q���āA�����i�S�����[�Y�H�j����{�^����V�[�����i���̉̕t�����I�j�A�ْ����������ă������B���炵���V�[�����Ǝv���܂��B
�܂��A�N�b�`���[�������e�Ŏ��Q����V�[���ŁA�����Ă������u�҂��Ă��璆�ɓ��ݍ��݁A�������U�镑�����A�ƍߎ҂ɑ����[���������������ۓI�ȃV�[���ł��B
�����āA�ׂ����ƌ��������Ȃ̂��V�������̃��`���[�h�E�N�����i�ł��B
�傫�Ȍ�����ł���`���̋�s�����̃V�[�����A���X�{�����}�ł̖����̃V�[�����ނ̊����ʂł���A�����Ƀh�k�[��������J�e�B�̏�v���ł�����A������̎���Ƃ����Ă��������炢�ł��B
�ނ̂悤�ȃA�����J�l�o�D�i�N�����i�̓C�^���A�n�j���������B����i�Ɏ剉�N���X�ŋN�p����邱�Ƃ͂قƂ�Ǐ��߂Ăƌ����Ă悢�قǒ��������Ƃł����A�������B���́A�N�����i�̏o�����Ă����e�����X�E�����O�ḗw�Â��Ȃ�܂ő҂��āx�i67�N�j���ύ����]�����Ă����悤�ł��̂ŁA���̂��Ƃ������āA�N�����i�ɔ��H�̖�𗧂Ă��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�m���ɑ��݊�������A�Ȃ��Ȃ��a�����͂����Ă͂���̂ł����A�����ȂƂ���A���l�͂��̉f����ς�x�ɁA�h�����ƃN�����i�̋����̃V�[���ɁA�����͂Ȃ����̂̉����������肱�Ȃ��ȁc�Ƃ����v�����@���Ȃ��̂ł��B
������������A���̓_����Ɏ����������悤�ȁA��l�̗F��W���f���Ƃ��ē`����Ă��Ȃ����ǂ������Ɍq�����Ă���̂�������܂���c�B

�J�g���[�k�E�h�k�[���́A�N�����i�̏�w�ł���Ȃ���A�Y���̃h�����Ƃ��W�����Ƃ��������J�e�B�������܂��B
�������B����i�ɔޏ��̂悤�ȃX�^�[���D���o�����邱�Ǝ��̒��������Ƃł����A��ɂ���āA���̐S�̒ꂪ���t�ŕ\������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���ʓI�ɁA�ޏ�����l�̒j�̂ǂ���ɕt���̂��A�Ō�܂Ńn�b�L�����܂���B
���̂����ł��傤���A�ޏ��̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ�Ǝv���邢�����̃V�[�����A�ǂ������ɂ͖��͓I�Ƃ͊������Ȃ��̂ł��B
��ɋ�����3�l�̎�������������V�[���������ł����A�h�����Ƃ́g�����L�b�X�h�̃V�[����A�z�e���ł̖���̃V�[���ȂǁA�������́g������h���A���҂����قǂ͗ǂ��V�[���Ɍ����Ȃ��͎̂������ł��傤���B
�����Ɓg�j�̉f��h���B���Ă����������B���ɂƂ��āA�J�g���[�k�E�h�k�[���Ƃ����X�^�[���D�āA�ǂ������Ɏ��߂�ׂ����A������������������o�Ă��܂����̂ł��傤���B
���������Ӗ��ł́A�h�k�[���l�̐ӔC�Ƃ������́A�r�{���S�������������B���̐ӔC�͑傫���ł��傤�B
�����Ƃ��A�h�k�[���͎B�e���A��̃L�A���E�}�X�g�������j��D�P�����������߂ɁA���܂蓮���̂Ȃ����ƂȂ����悤�ŁA���̉e��������������܂��c�B
�ȏ�A�剉��3�l�ɑ��ďq�ׂĂ��܂������A���̍�i�́A�ӊO�Ȃقǘe�����[�����Ă����i�ł�����܂��B
�M�����O���̃A���h���E�v�b�X�A�}�C�P���E�R�����b�h���A�N�̋������݊��������Ă��܂����A���J���h�E�N�b�`���[���ƃV���[�k�E���@���[���̉�����i�\�ʏ�́j������ʓI�ȕv�w�����A����܂ł̃������B����i�ɂ͂Ȃ��s�v�c�Ȗ��킢�Ɖ��s�����f��ɂ����炵�Ă��܂��B
�܂��A�I�J�}�i�H�j�̏���̃��@�����[�E�E�B���\���̈�ۂ��Ȃ��Ȃ��N��ł��B

���ɁA�V���[�k�E���@���[���̎������̕v�ł���W�����E�h�T�C���A�������҂̐a�m���Ń����V�[���̂ݏo�����Ă��܂��B
�w���ʁx�Ōx�������D�����Ă����h�T�C���Ăу������B����i�Ɋ���o���Ă��ꂽ�̂̓t�@���ɂƂ��Ă͎��Ɋ��������Ƃł����A���ꂾ���ɏo���V�[�����Z���̂��Ȃ�Ƃ��c�O�ł��B
����ł��h�����Ƃ̃c�[�E�V���b�g������ꂽ�̂ł悵�Ƃ��܂��傤�B
�ȏ�A���X�Ə����Ă��܂������A�������̖��͓I�ȃV�[���̂���f�悾���ɁA�Ȃ�Ƃ��ɂ�����i�ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����v�����ǂ����Ă������܂���B
���̍�i���������B���̈��ɏI��炸�A���̌���������̌�����c���Ă���A�u�w���X�{�����}�x�̓C�}�C�`�������˂��v�ōςޘb�������̂�������܂��A������i�̏��Ȃ��������B���́A���ɂ���Ĉ��ƂȂ��Ă��܂�����i�����ɁA�t�@���Ƃ��Ă͌��ʂĂʖ���ǂ��Ă��܂��Ă���̂�������܂���c�B |

|
| ���炷�� |
�������J���~�蒍���A12��23���̌ߌ�B
�T���E�W�����E�h�E�����̊C�݉����ɂ��閳�@�I�ȃ}���V�����̈�Q�ɁA4�l�̒j���悹�����̎ԁi�N���C�X���[�j��������B
����A�N���X�}�X��O�ɓ��키�p���ɂ́A�p�g���[�����̃R�[���}���Y���B
�������܂��A�V���Ȏ����̔�����m�点�閳���d�b����A�ނ̈�����n�܂�B
�T���E�W�����E�h�E�����B
��قǂ̃N���C�X���[����\�t�g�X�Ƀg�����`�R�[�g�p�̃V�������܂��~���B
���̂悤�Ȗ\���J�̒��A��������̓}���V�����̈�p�ɂ����s�ł���B
��s�̒��ɓ���ƁA�q���đ��ۂ̃J�E���^�[�Ɉʒu���߂�B
�X�ԍۂƂ������Ƃ������āA��s�̒��̐l�e�͂܂炾�B
��l�ڂ̒j�}���N���Ԃ���~���B
�V�����Ƃ͂킴�Ǝ��Ԃ����炵�A������܂���s�̒��ւƓ���B
�O�l�ڂ͋C�セ���Ȓj�|�[�������A�Ԃ̒�����o��̂���u�S�O����B
�^�]��̃��C�̎����ɑ������悤�ɁA�ӂ������ĎԂ��~���s�ւƌ������B
�|�[������s�ɓ���̂����}�ł������̂��A��ɓ������V�����ƃ}���N�͖����ɃT���O���X�Ől�����B���B
�X���ԂƂ������Ƃ�����A�قƂ�ǂ̋q�͋�s����ɂ��A��s�̊O�̓V���b�^�[���܂�B
���̏u�ԁE�E�E
�T���O���X�ƃ}�X�N�Ől�����B�����j3�l���A�s���ɏe�������A����v�����饥���s�������B
�������ɋ����A�f���ɋ����o���s�������B
�������A�������āA�o�[�W�̍s�����D�����x��@�̐Ԃ��{�^���ɓ������A�������܂������x������B
�ǂ̉e�ɉB�ꂽ��قǂ̏o�[�W�͉B���Ă������s�X�g������Ɏ��ƁA�}���N�ڊ|���Č��B
�}���N����l�ɏo�[�W�ڊ|���ċ@�֏e�𗐎˂��邪�A�����Ȃ�̏e�������߂��B
�D���̓������܂�D���������Ƃ����͑҂������Ă������Ԃɏ�荞�݁A���̏������B
�����ꂽ�}���N�͂��Ȃ�̏d���ł���B
�Ƃ��钬�̉w�ɎԂŏ����������Ƃ�́A�p���܂ł̐ؕ����ė�Ԃɏ��J���t���[�W�������āA�ԂɍĂя�荞�݁A����������B
�ނ�͂Ƃ���n�Ɍ����@��A��ɓ��ꂽ������U�����։B���A�d�������}���N�͕a�@�ɔ��������B

��̃p���B
�p�g���[�����̃R�[���}���Y���̎ԂցA�܂���������m�点�閳���d�b����B
���̓��̎����́A�ꖖ�̃z�e���ł̔��t�w�炵�������̎E�l������A�a�m�Ə��N�̓��������t������g���u���Ȃǂ��B
�X�̗��p�ɎԂ��߂��R�[���}���̌��ցA���i�H�j��M���r�[���^�]����Ԃ�������B
�M���r�[�́A���X�{���s���̓��}��ԂŖ��^�э��܂��Ƃ��������R�[���}���ɒm�点��B
�^�щ��̂������́g�^�щ��}�`���[�h������N�^�т̐��ƂŁA�Ŋ֗����O�����Ƃ����B
�R�[���}���ɂƂ��āA�M���r�[�͋M�d�ȏ�i���ʁj�̂悤���B
�x�����̃R�[���}���̃I�t�B�X�B
���̓��̈Č��͋�`�X����3�l�g�ŁA�ꌩ���ĊO���l���ł���A�t�����X�ꂪ������Ȃ��ӂ�����Ă��邪�A�R�[���}�����\�͂ɑi����ƁA�����ɉR���I������B
�����Ƃ̈�l�A�|�[���E�E�F�x���̃A�p�[�g�B
�ȑO�߂Ă�����s�����X�g������A�\�����͐V���ȐE��T���Ă���悤���B
�Ȃ͕v�̍ďA�E��S�z���Ă���B
���������̏��Ƃł���T���E�W�����E�h�E�����ł̋�s������m�点��V�����p���̊X���Ŕ����A�����Ƃ̈�l�A���C�E�R�X�^�B
�F�l�ł���V�������o�c����i�C�g�N���u�ɗ������R�[���}���B
�X�͂܂��J�X�O�̏������̏�Ԃ����A�R�[���}���͊��ꂽ���͋C�œX�ɓ���ƁA�s�A�m��t�ł�B
������A���猩�Ă���V�����̏��A�J�e�B�B
��l�̖ڂ������B
�����֗����킷�X�̃I�[�i�[�A�V�����B
�R�[���}���ɂ́A�����̃���������d���ɖ߂�悤�Ñ����鐺��������B
�J�e�B�ɓ����L�b�X�����ċ����Ă䂭�R�[���}���A����ɉ�����J�e�B�B
��l�ɕ��G�Ȏ����𑗂�V�����B
�R�[���}������������A�V�����̓J�e�B�ɁA���炪���s�����T���E�W�����E�h�E�����ł̋�s�����̋L���̏o�Ă���V���������邪�A�J�e�B�͉����������m���Ă���悤���B
���[�������p�ق̊ٓ��B
�����փV�����A�|�[���A�R�X�^��3�l�������킹�A���k������B
���@�������}���N�Ɍx�@�̎肪�����Ă��邪�A�ʂ̏ꏊ�ɂǂ�����Ĉڑ����邩����������ꂪ�����Ȃ祥��B

�ˌ���ő������̗��K�����Ă���R�[���}���̌��֓d�b��������B
�u�����͂܂������A�����Ȃ�v
�N���Ɖ�����Ă���炵���B�i��ɓd�b�̑��肪�J�e�B�ł��邱�Ƃ�������j
�}���N�̓��@���Ă���a�@�ɎԂŏ������V������B
�V�����ƃ��C�́A��҂ɕϑ����A�f�������[�������T�C�������Ƃ����U�����ނ��g���āA�V���~�b�g�i���@�����ۂ̃}���N�̋U���j�̈ڑ�����邪�A�w���炵���Ō�w�ɁA���҂̐�Έ��Â𗝗R�Ɉڑ���f���Ă��܂��B
�ڑ��������ƌ����A�Ō�w�̕����������J�e�B���}���N�̕a���ɔE�ѓ���A������Ԃ̃}���N����C���˂Ő▽������B
�@��w�������̊ӎ��ۂŁA�V���~�b�g�̎��̂��m�F����R�[���}���ƃ����������A�g���̔����͓�������B
����ȍ��A���C�͐V���Ȕƍs�ɕK�v�ȎԂ�T���Ă���B
�R�[���}���͂���z�e���̈ꎺ�Ɍ������B
�����ő҂��Ă����̂̓J�e�B�ł���B
����������l������͓�l�͒j���̒��������̂��B
�V�����ɋC�Â���邱�Ƃ������J�e�B�����A�R�[���}���͂��łɋC�Â���Ă���ƌ����B

�x�O�̂���Ƃ̒��őł����킹������V�����A���C�A�|�[����3�l�B
�g�^�щ��}�`���[�h�����X�{�����}�Ń��N���^�ԏ��͔ނ�ɂ������Ă���A���̃��N���ԓ��ʼn���肷��v��𗧂ĂĂ���̂��B
���ꂪ�\�Ȃ̂̓{���h�[�ƃX�y�C���Ƃ̍����̊ԁA������A�����b�g�ƃ����T���X�̊Ԃ�65�L�����B
���i�Ȃ��Ԃ͎���150�L���Œʉ߂���Ƃ��낾���A���͍H�����Ȃ̂ŁA����30�`60�L�������o���Ȃ��B
���s�\�Ȏ��Ԃ�20���B
��ɓ��ꂽ�u�c�͒D�����������{�l�ɔ������悢���A��������A�ǂ����������͏o���A�x�@�ɂ�������Ȃ��E�E�E�B
�Ăя�M���r�[����̏�����R�[���}���B
��́g�^�щ��}�`���[�h�̏���Ԃ́A�p���̃I�[�X�e�����b�c�w23��59�����̃��X�{�����}�ŁA�{���h�[�ɒ����̂�5��43����������Ń}�`���[�̓u�c�����̂��Ƃ����B
�������ɎQ������|�[���́A���x�E�T���̂��ߖ�s�ɏ�邱�ƂɂȂ����A�ƍȂɉR�����B
�V�����̃i�C�g�N���u�ł́A�J�e�B���V�����̍��x�̎d����S�z���Ă���B
�����֗����킹���R�[���}���B
3�l�̓J�E���^�[�ň��ݎn�߂邪�A3�l�̎����́A���̔����ȊW�����������Ƃ��A�ǂ�����܂�Ȃ�����B

�J�̒��A�ԂŃ{���h�[�ւƌ������V�����A���C�A�|�[����3�l�B
�p���̃I�[�X�e�����b�c�w�ł́A�g�^�щ��}�`���[�h��23��59�����̃��X�{�����}�A�Q��̌��ɏ�荞�ށB
�R�[���}����x�@�́A�{���h�[�w�̃v���b�g�z�[���ŗ�Ԃ�҂ӂ�����ėl�q���M���B
�����ɁA���N��n����͂��ɂȂ��Ă���M�����O�A�����v���b�g�z�[���ŗ�Ԃ�����̂�҂��Ă���A��Ԃ���܂�ƁA���l�̃M�����O���}�`���[�Ƀ��N��n�����ߗ�Ԃɏ��B
�n���ꂽ���N�̑܂����̒��ɋl�߂�}�`���[������g�̓w���C���̂悤���B
�{���h�[�w�Ń��N���n�������Ƃ����͂����R�[���}���́A�n�����̘A���Ɍ��C����ƁA�p���ւƖ߂�B
�{���h�[�w���o���������X�{�����}�̔w��Ɉ�@�̃w���R�v�^�[������B
����Ă���̂́A�V�����A���C�A�|�[����3�l���B
�ʒu���߂�ƁA�w���R�v�^�[�����Ԗڊ|���č~������V�����B
��Ԃ̉����ɍ~�肽�V�����́A�ړI�̎ԗ��̃X�e�b�v���璆�ɏ��ƁA�g�C���ʼn���𗎂Ƃ��A�K�E���ɒ��ւ��āA���J�ɐg�Ȃ�𐮂��A��q�ɐ���ς܂��B
�����̂��ߎc���ꂽ���Ԃ͂���10���B
�������A�����֕ʂ̏�q�������킹�Ă��܂��A�߂�����܂Ŏ��Ԃ�����Ă��܂��B
�V�����́A���̏�q������̂�҂��āA�}�`���[�̌��̑O�ɗ��ƁA�����g���Ē��̍������O���A�������g���Ē��ɓ���A�������܃}�`���[�������Ď��_������B
�C�₵���}�`���[�̌��ƕ@�ɃK�[�[��\��t���A�N�����z�����𐔓H���Ƃ��B
���N�̓��������̊����D���ƁA�Ăуg�C���ɓ���A��ԐZ�����Ɏg�����C���ƒ��ɍĂђ��ւ���B

��Ԃ̃X�e�b�v�ɏo���V�����́A�w���R�v�^�[�ɉ����d���ō��}�𑗂�ƁA�w���R�v�^�[����̓U�C�����~��Ă��āA����Ƀ��N�̓��������̕���ʂ��A�w���R�v�^�[�ւƑ���Ԃ��B
�w���R�v�^�[���Ŋ���������|�[���́A�Ăї�Ԃ̃X�e�b�v�őҋ@���Ă���V�����̉��ւƃU�C�����~�낵�A�����`���āA�V�����͐������ԃM���M���Ńw���R�v�^�[�ւƖ߂�B
��ԓ��ł́A�ӎ������߂��A���N��D��ꂽ���Ƃ�m��A���_����}�`���[�B
����A�V������́A������l�̒j�Ɩ����ꏊ�Ńw���R�v�^�[����~���ƁA�҂����Ă������Ԃɏ���ē�������B
�R�[���}���̃I�t�B�X�ɃM���r�[���Ă��B
�Ȃ��Ăꂽ�̂������ł����ɂ���M���r�[�̊���ł����Ȃ艣�����R�[���}���B
���̌�A�x�@�̓A���_�C���ʼn^�щ��}�`���[��ߕ߂������A���N�͂ǂ�������o�Ă��Ȃ������̂ŁA�M���r�[���K�Z���𗬂����ƐM������ł��܂����̂��B
�Ȃ�������̂������ł��Ȃ��ƌ�������M���r�[�����A�p����������{��S���̃R�[���}���ɂ͒ʂ��Ȃ��B
�M���r�[�́A�R�[���}���̃I�t�B�X���瓊���o����A���ӂ̂����ɂ���������B
����Ȏ��A�ӎ��ۂ���A�R�[���}���̌��փV���~�b�g�̌������������Ă���B
���͎̂��̓}���N�E�A���u�C�Ƃ����j�ŁA�ʐ^�����ăR�[���}���́A���C��R�X�^�̗F�l���ƚk������B
��̋�s�����Ɗ֘A������̂ł́H�ƍߑ{���ۂɈ˗������ẮH�Ƃ����������ɑ��āA���b�ȑԓx�����R�[���}���B
�����������̏����������A�}���N�ƃ��C�Ƃ̊W���C�Ɋ|����R�[���}���̓V�����ɓd�b�����邪�A����B
�������ܕ����ɂ��d�b�����āA�}���N�̌��͐V���ɂ͓����ɁA�ƈ˗����悤�Ƃ��邪�A�����ɒx�������B
�V���Ɂu��s�����̕Њ��ꂩ�H�v�ƃ}���N�̋L�����ڂ��Ă���̂���ɂ��郋�C�B
�H���̂��߁A���郌�X�g�����ɓ��邪�A������ɔ����āA�e���B�������Ă���B
����Ȏ��A���m�W�̏��������̋q�ɓd�b�̎掟��������B
�u�W��������A���Ȃ��ɂ��d�b�ł��v
�Ƃ��낪�A�W�����Ƃ́A���C�����̓X�ɗ��邱�Ƃ�z�肵�āA���̃��X�g�����ɋq�ɐ���ς܂��ĔE�э���ł����R�[���}���ł������B
���C�̔w�ォ��H�����i�߂ɂ��Ď�艟������R�[���}���B
���C���B�������Ă����e�͂����ɉ�������A���C�͐��l�̌Y���ɂ���đߕ߂����B

�x�����A�R�[���}���̃I�t�B�X�ɘA�s����郋�C�B
���C�̎����̂̑O�ɂ����������A�����������C�̏e�����R�[���}���B
�����ŏe����e�q���A�e�g�̒��g�������B
��������Ȃ���A�]�T�����܂��A�j�������C�B
�R�[���}���́A���C�̊�����̊�����\�����A���\��Ō���B
�����ނ�Ƀ��C�̂��܂Ŋ��ƁA�����i�S�����[�Y�H�j�����C�ɓn���A�����Ă��ƁA�܂��́A��s���������������悤�Ƃ���B
�u���_�͒N���H�v�Ɩ₤�R�[���}���ɑ��A�����郋�C�B
�u�}�W���H���ɉ����ւ���Ă���Ƃ��āA���Ԃ�Ƃł��H�v
�u�q���邩�H�v������M���X�̃R�[���}���ɐ��_�I�ɈЈ�����郋�C�B
���C���߂܂����j���[�X��m�����V�����ƃ|�[�����ȑO�̂���ƂŎ��������c���Ă���B
���C�͓f���Ȃ��ƐM���Ă���V���������A�|�[���͂ǂ����s�������B
�����߂��A��ɂȂ�A�V�����̓X�Ɍ��ꂽ�R�[���}���B
�����̂悤�ɃV�����Ɠ�l�ň��ݎn�߂邪�A�����Ȃ��o���B
�u�}���N�E�A���v�C�̂��Ƃ�m���Ă邩�H�v
�u����v���������V�����B
�u�|�[���E�E�F�x���́H���X�g�����ꂽ����s�̓X���⍲���B�v
�u�S���������ȁv����܂���������V�����B
��l�̊Ԃɔ����ȋ�C�������B
�u����A���C��R�X�^�́H�v
�u�R�X�^�A�R�X�^�������ȃ��c�͒m��Ȃ��v�������܂�������V�����B
�u���c�͂��O�̂��Ƃ�m���Ă��邼�v
���ꂾ�������āA�X�𗧂�����R�[���}���B
�����̃I�t�B�X�ɖ߂����V�����͂������܃|�[���ɓd�b����ƁA���傤�NjA�������̃|�[�����d�b�ɏo��B
�u�|�[���A���C���f�����v
�u�܂����v����v�̗l�q��s���C�Ɍ��߂�|�[���̍ȥ���B
�u������A�|�[���v
����Ȏ��A�|�[���̃A�p�[�g�̑O�ɒ�܂�x�@�̎ԁB
�u�����x���B���}�����v
�u�������������A�|�[���B�܂��ȁv
�����œd�b��u���|�[���B
�|�[���̕����̃x������A�Ȃ����ւ��J����ƁA�R�[���}����x�@�����ɐ���ꍞ��ł���B
�����x���Ǝv�����|�[���͌��e������Ɍ�����B

�����A�M���傻��splended hotel�B
�������ɔ�����邽�߂̖�������ɋl�߂�V�����B
�J�e�B�Ɍ}���ɗ���悤�d�b�����邪�A���̘b�̓��e�̓R�[���}����x�@�ɓ�������Ă���B
�z�e���̑O�ŃJ�e�B��҂V�����B
�ʂ�̌��������ɎԂŏ��t����J�e�B�B
���̎��A�R�[���}������납�琺���|���饥��u�V�����A�҂āv
�e���V�����Ɍ����u�����ȁA�V�����v
��������Ɏ����Ă䂭�V�����A���̏u�ԥ���R�[���}���̏e���𐁂��B
�|���V�����B
�R�[���}���琔�l���삯���m�F���邪�A�V�����͊ۍ��������B
�u���܂�����H�v�ƃ������ɖ���A
�u�Ă����艴�����C���Ɓv�E�E�E��R�Ƃ���R�[���}���B
�����ւ����̂悤�Ƀp�g�J�[�ɕʂ̎�����m�点�閳���d�b��������B
�ʂ�̌��������ɂ���J�e�B�ƃR�[���}���̖ڂ������B
�����̓�l�B
�J�e�B�͖ڂ��A���ނ����܂܁B
�M������o�b�N�ɃV�����[���[�ʂ���ԂŌ�ɂ���R�[���}���ƃ������B
�F�Ɨ��l�̓�l���Ɏ������R�[���}���͕�R�ƎԂ𑖂点��B
���������K�������߂邪�A�R�[���}���͎�����ɐU��B
�V���Ȏ�����m�点�閳���d�b�̃u�U�[���Ăі邪�A�R�[���}���̋C�����𗶂����������͓d�b����莟���Ȃ��B
 |
|

